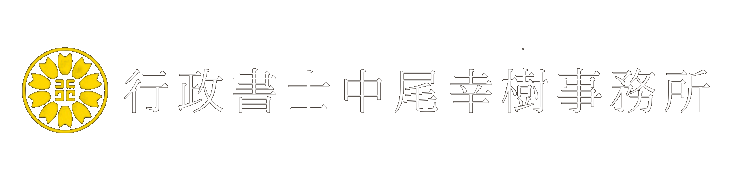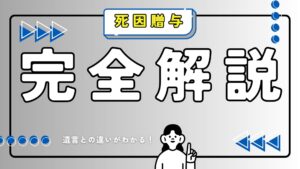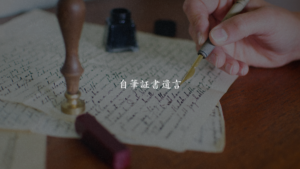SCROLL
遺言。聞いたことはあるけど、難しそう…。
でも、大切なのは知ること。
今から正しい知識を身につけて、あなたの大切な想いを確実に伝えましょう。
こんな
お悩み
解決します
相続人の調査
相続関係説明図作成
相続人の確実な確認には、専門家による戸籍収集と調査が不可欠です。時間の節約と正確性を両立し、安心の相続サポートをご提供します。
相続財産の調査
財産目録作成
財産目録の作成と遺言書との照合により、故人の本意を汲み取った公平な遺産分配が可能になります。目録化は視覚化にも役立ち、適切な財産把握に欠かせません。
遺言作成サポート
遺言者の最終意思を法的に有効な形で反映した遺言書を作成するには専門家に依頼することが重要です。専門家の関与は、円滑な遺産相続と遺族間の紛争防止にも役立ちます。
安心サポート
遺言書作成は心身ともに大きな負担がかかります。しかし、専門家が細部までサポートすることで、「遺言書を作って良かった」と心から実感していただけるでしょう。全力でお手伝いさせていただきます。
遺言執行人
相続の面倒な手続きは、専門の行政書士に包括的にお任せください。私どもが遺言に基づき、相続人に代わって丸ごと手続きを代行させていただきます。ご安心してお任せいただけます。
他士業との連携
不動産登記や相続税の手続き、他の専門家との連携が必要な場合でも安心してお任せください。必要に応じて適切な専門家を手配し、お客様に一から専門家を探す手間はかかりません。
推定相続人の調査
相続関係説明図の作成
推定相続人の把握と、書類収集、相続関係説明図を作成します
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集めます。これは私たちの専門知識を使って行います。そして、相続に関わる人を全て見つけ出します。
次に、誰が相続人になるのかを図で分かりやすく示します。この図を「相続関係説明図」と呼びます。これにより、相続人を間違いなく把握できます。
お客様の代わりに、私たちが正確に戸籍を調べ、相続に関わる人を特定します。

相続財産の調査
財産目録の作成
遺言に必要な相続財産の調査、財産目録の作成します
相続では、亡くなった方の財産だけでなく、借金なども調べる必要があります。これらをしっかり把握することが大切です。
もし遺言に書かれていないことがあれば、相続人全員で話し合って決めなければなりません。私たちの事務所では、銀行やお金を扱う会社、役所などから細かく調べます。そして、亡くなった方が持っていた財産や借金の一覧表を作ります。
相続の手続きは複雑で面倒なものです。でも心配いりません。私たちがお客様に代わって手続きを行い、スムーズに相続が進むようお手伝いします。

遺言書の作成サポート
遺言書の原案を作成します
遺言書には自筆、公正証書、秘密証書の3種類がありますが、構成要素は大きくは変わりません。ただし遺留分のアドバイス、執行者の権限設定、付言の添え方など、遺言の効果を最大限引き出すには専門知識が不可欠です。遺言の専門家が適切にサポートすることで、円滑な遺言執行が可能となります。

安心のサポート
ご不明点はなんでもご相談ください
遺言や相続に関するご不安は何でもご相談ください。私の目標は、遺族間の紛争防止と、大切な方を亡くした家族が1日でも早く平穏を取り戻れるようサポートすることです。大切な人との最期の別れを穏やかなものにするため、全力でお手伝いいたします。

遺言執行人
遺言書の原案を作成します
遺言の内容は相続人の意思より原則優先されます。故人の想いを汲み取り、滞りなく実現するのが遺言執行人の務めです。面倒な手続きは全て代行しますので、相続人の方々に無用な手間をおかけすることはありません。

それぞれのプロへ
ワンストップ、それぞれの専門家へお繋ぎします
契約後も相続や遺言に関するお悩みがあれば気軽にご相談ください。複雑な案件は時間を要しますが、お客様の不安解消に全力を尽くします。また、登記や税務、トラブル対応が必要な際は、適切な専門家と連携してスムーズな対応を心がけます。

\
いつでも
ご相談ください
/
手続き開始までの流れ
User Guide
ご依頼までの
ステップガイド
わからないことは何度でも聞いてください。疑問点をクリアにし気持ちよくご契約いただけるよう努めてまいります。
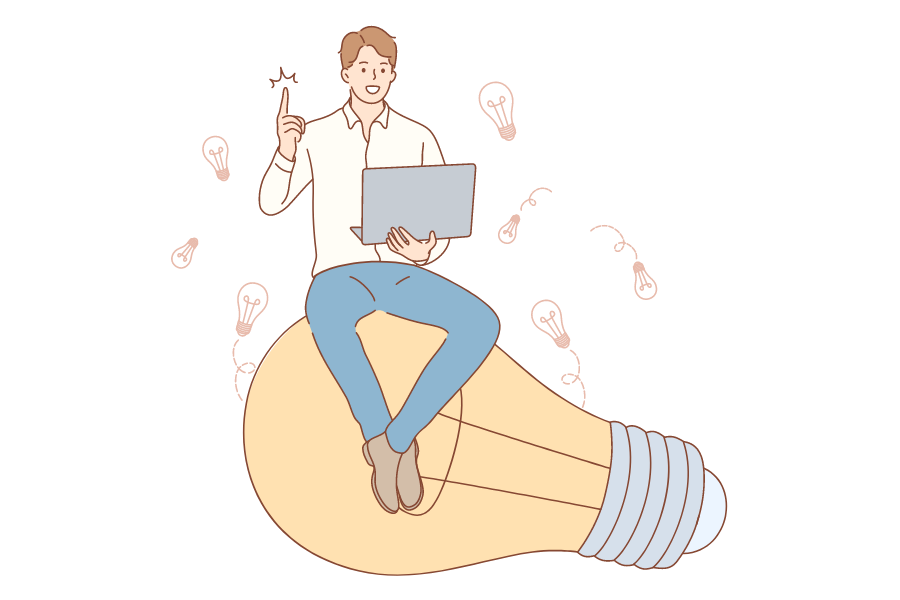
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINEまたは電話でご連絡ください。
面談日の調整
- 面談日を調整させていただきます。
- ご自宅への訪問、電話やWebでの面談まで柔軟に対応させていただきます。
ヒヤリング
ご相談内容をお気軽にお話しください。
お見積もり
ヒヤリングの結果を基に、お見積りを提示します。
ご契約
- ご契約内容の確認と報酬額に納得いただければ契約書を取り交わします。
- 今後の流れと必要なものをご案内させていただきます。
着手金支払い
着手金をお支払いいただきます。着手金は一律4万円とさせていただいております。
業務着手
着手金のお振込を確認でき次第、速やかに業務に着手します。
報酬
私たちの事務所で一番大切にしているのは、「家族の絆を守る」ということです。
そのために最も確実な方法が遺言を残すことです。
「遺言を作るのになぜこんなにお金がかかるの?」「高すぎるから自分で作ったほうがいいのでは?」
そう思われるかもしれません。
でも、遺言は法律で決められたことをしっかり守り、正確に作らないと意味がありません。
そこで私たちの事務所では、まず基本的な料金とサービスの内容をはっきりお伝えするところから始めます。
そして、細かい費用については「報酬額表」という表を公開して、誰でも見られるようにしています。
全部でいくらかかるかは、この料金表を見れば分かります。
分からないことや気になることがあれば、いつでも聞いてください。
自筆証書遺言作成サポート
最小限の費用で済ませたい方
39,000円
| 遺言書原案作成 | ○ |
| 相続人調査 | |
| 相続関係説明図 | |
| 相続財産調査 | |
| 財産目録作成 | ○ |
| 遺言執行人指定 | |
| 遺言書保管制度 | |
| 証人 | ー |
| 公証役場立会 | ー |
自筆証書遺言が法律の定めに従った正しい形になっているかの確認を行います。財産や相続人の調査など全てご自身でお調べいただき相続において費用を最小限にしたいとお考えの方だけににおすすめしています。
公正証書遺言サポート
確実な遺言を残したい方
110,000円
| 原案作成 | ○ |
| 相続人調査*1 | ○ |
| 相続関係説明図作成 | ○ |
| 相続財産調査*2 | ○ |
| 財産目録作成 | ○ |
| 遺言執行人指定 | |
| 遺言書保管制度 | ー |
| 証人*3 | ○ |
| 公証役場立会 | △ |
相続人調査、相続情報説明図、財産調査、財産目録の作成まで行います。確実に法定相続人を把握し財産をまとめ、遺留分等を考慮した確実な遺言を残したい方へおすすめしています。
*1 相続人調査は法定相続人3名までをプランに含みます。詳細は報酬額表をご覧ください。
*2 財産調査は3件までをプランに含みます。詳細は報酬額表をご覧ください。
*3 証人は担当する行政書士1名を料金に含みます。詳細は報酬額表をご覧ください。
報酬は税抜での表示となっております。別途消費税10%頂戴いたします。
よくある質問
FAQ