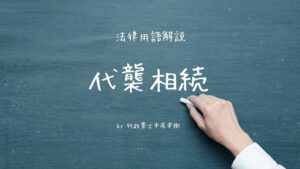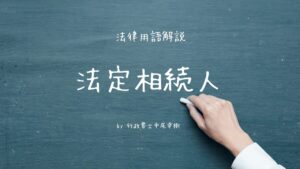「法定相続人」って何?知っておきたい
相続の基本と大切なポイント
相続に関する話を聞くと、難しそうだと感じる方も多いでしょう。でも、実は知っておくべき大切な情報なのです。
特に「法定相続人」という言葉、耳にしたことはありませんか?これは、亡くなった方の財産を受け継ぐ権利がある人のことを指します。
誰が相続人になるのか、どのように決まるのか。知っておくと、将来の備えになります。
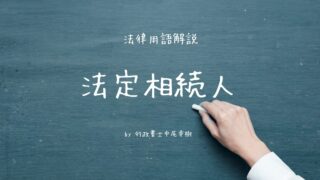
- . 「法定相続人」って何?知っておきたい 相続の基本と大切なポイント
- 1. 1. 法定相続人とは?基本をおさえよう
- 1.1. 1-1. 法定相続人の定義:誰が相続できる?
- 1.2. 1-2. 相続順位:3つの典型例で解説
- 1.2.1. 例1:配偶者と子供がいる場合
- 1.2.2. 例2:配偶者はいるが子供がいない場合
- 1.2.3. 例3:配偶者も子供もいない場合
- 2. 2. 法定相続分を簡単に計算しよう
- 2.1. 2-1. 相続分の基本ルール
- 2.2. 2-2. 具体例で見る相続分の分け方
- 3. 3. 代襲相続って何?知っておきたいポイント
- 3.1. 3-1. 代襲相続の仕組み
- 3.2. 3-2. どんなときに起こる?具体例で理解
- 4. 4. 遺留分制度:相続で押さえておくべき基礎知識
- 4.1. 4-1. 遺留分って何?表で簡単チェック
- 4.2. 3-2. 実際いくらになるの?遺留分額を計算する
- 4.3. 4-2. 代襲相続があったときの遺留分
- 5. 5. 相続Q&A:よくある疑問にお答えします
- 5.1. 5-1. 養子も相続できる?養子と実子の違い
- 5.2. 5-2. 相続放棄のメリット・デメリット
- 6. 6. まとめ:相続の基本をおさらいしよう
1. 法定相続人とは?基本をおさえよう
1-1. 法定相続人の定義:誰が相続できる?
法定相続人とは、法律で定められた相続権のある人のことです。
簡単に言えば、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐことができる人たちのことです。
法定相続人になれる人:
- 配偶者(夫または妻)
- 子供
- 父母
- 兄弟姉妹
- 祖父母
ただし、これらの人が全て同時に相続人になるわけではありません。次に、相続の順番について見ていきましょう。
1-2. 相続順位:3つの典型例で解説
相続には順位があり、上位の人がいる場合、下位の人は原則として相続人にはなれません。以下、典型的な3つの例を見てみましょう。
例1:配偶者と子供がいる場合
相続人:配偶者と子供
順位:1位(同順位)
これが最も一般的なケースです。配偶者と子供が同じ順位で相続人となります。
例2:配偶者はいるが子供がいない場合
相続人:配偶者と被相続人の父母
順位:配偶者(1位)、父母(2位)
子供がいない場合、配偶者と被相続人の父母が相続人となります。
例3:配偶者も子供もいない場合
相続人:被相続人の父母
順位:父母(1位)
配偶者も子供もいない場合、被相続人の父母が相続人となります。
父母もいない場合は祖父母、さらにいない場合は兄弟姉妹(おい、めい)が相続人となります。
2. 法定相続分を簡単に計算しよう
2-1. 相続分の基本ルール
法定相続分とは、法律で定められた相続財産の取り分のことです。
相続人が複数いる場合、以下のルールで分けられます。
基本的な法定相続分:配偶者は常に法定相続人の第1順位です。
配偶者と上位順位の人が法定相続人となります。下位の順位の人は基本的に相続放棄などが無い限り相続人にはなりません。
配偶者がいない場合には上位の順位の相続人が財産を相続します。
| 相続人の順位 | 相続人 | 配偶者がいる場合の例 |
|---|---|---|
| 第1順位 (子) | 配偶者 | 2分の1 |
| 子(直系卑属) | 2分の1(子が複数いる場合は均等に分配、例:子2人=1/4ずつ) | |
| 第2順位 (第1順位がいない場合) | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母(直系尊属) | 3分の1(父母がいる場合は均等に分配) | |
| 第3順位 (第1順位、第2順位がいない場合) | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分配) |
2-2. 具体例で見る相続分の分け方
実際の例を見てみましょう。
例:夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人の場合
妻の相続分:1/2
子供たちの相続分:残りの1/2を2人で等分(各1/4)
つまり、1億円の遺産があった場合: 妻:5000万円 子供A:2500万円 子供B:2500万円 となります。
3. 代襲相続って何?知っておきたいポイント
3-1. 代襲相続の仕組み
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に亡くなっていたり、相続権を失っていたりした場合に、その人の子供が「代わりに」相続人となる制度です。
代襲相続のポイント: 亡くなった相続人の権利を引き継ぐことができます。例えば、亡くなった人の子が法定相続人である時、子が相続放棄を行ったら相続人の権利はその子供に当たる孫が取得します。尚、兄弟姉妹には代襲相続はありません。
3-2. どんなときに起こる?具体例で理解
例:父親が亡くなり、長男も既に他界している場合
相続人:妻、長男の子供(孫)、次男
相続分:妻(1/2)、長男の子供(1/4)、次男(1/4)
この場合、長男の子供(孫)が代襲相続人となり、長男が受け取るはずだった相続分を相続し次男(長男の弟)と1/4ずつもらえます。
4. 遺留分制度:相続で押さえておくべき基礎知識
4-1. 遺留分って何?表で簡単チェック
遺留分とは、遺言書などで相続分を指定されても、最低限保障される相続分のことです。
相続や遺言作成、家族信託契約時にはこの遺留分をどれだけ考慮し柔軟な遺言を作成、信託契約書を作成するかで後の争族を防ぐポイントとなります。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | 法定相続分の1/2 |
| 子供 | 法定相続分の1/2 |
| 直系尊属(親、祖父母) | 法定相続分の1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし |
3-2. 実際いくらになるの?遺留分額を計算する
遺留分の計算はシンプルです。
例えば、夫が亡くなり妻と子供1人がいる家庭。
夫は遺言で妻に全財産(自宅2000万と現金1000万)を相続させると遺しています。
被相続人:夫
相続人:妻と子
相続財産:自宅2,000万、現金1,000万
このような遺言は相続権をもつ子(1/2)の権利を侵害していますが、遺言的に無効とまではなりません。ただし、子供から遺留分侵害請求という自分の最低限の取り分を請求されるかもしれないという点は覚えておいてください。
子の持つ遺留分額は全財産3000万に法定相続割合1/2と遺留分1/2をかけた額、750万円という事になります。従って妻はこの750万円をどのように支払うかが問題となります。
現金は1000万しかありません、子に750万を支払うと250万と自宅しか残らないのです。
4-2. 代襲相続があったときの遺留分
代襲相続の場合、代襲者(例:孫)は本来の相続人(例:子)と同じ遺留分を受け継ぎます。つまり、孫の遺留分も法定相続分の1/2となります。
重要ポイント: 代襲相続人の遺留分は、本来の相続人と同じ 複数の代襲相続人がいる場合は均等に分ける
5. 相続Q&A:よくある疑問にお答えします
5-1. 養子も相続できる?養子と実子の違い
養子の相続権: 養子も実子と同じ相続権を持ちます 法定相続分も実子と変わりません ただし、相続税の計算で一部異なる扱いがある場合があります
5-2. 相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄とは、相続の権利を放棄することです。
メリット: 被相続人の借金を引き継がなくて済む 相続税の負担を避けられる
デメリット: 一度放棄すると取り消せない 財産も相続できなくなる
相続放棄を考えている方は、必ず専門家に相談しましょう。
6. まとめ:相続の基本をおさらいしよう
今回、法定相続人について学びました。
主なポイントは: 法定相続人は法律で定められた相続権のある人 相続には順位があり、上位の人が優先される 法定相続分は配偶者が1/2、残りを他の相続人で分ける 代襲相続は、本来の相続人の権利を引き継ぐ制度 遺留分制度は、最低限の相続分を保障する
相続は複雑な問題です。分からないことがあれば、相続専門の行政書士など専門家に相談することをおすすめします。
「孫が相続人?【代襲相続】とは| 誰もが知っておくべき相続の仕組み」
法定相続人と相続人の違いを解説|逗子市の相続手続き専門行政書士
遺留分の基礎知識
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。