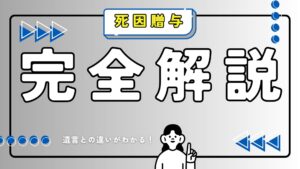生前贈与をご存知ですか?これは、まだ元気なうちに自分の財産を家族や大切な人に贈ることができる制度です。相続税の節税対策としても注目されています。しかし、正しい知識がないと思わぬ落とし穴にはまることも。この記事では、生前贈与の基本から注意点まで、わかりやすくお伝えします。老後の安心と家族の幸せのために、ぜひ参考にしてください。
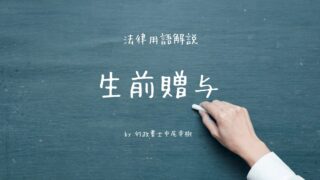
- 1. 1. 生前贈与とは?4つの贈与方法の中の1つ
- 2. 2. 生前贈与のメリット・デメリット
- 2.1. 2-1. メリット:相続税の節税になる
- 2.2. 2-2. メリット:早めに財産を渡せる
- 2.3. 2-3. デメリット:贈与税がかかる可能性がある
- 3. 3. 生前贈与の種類と特徴
- 3.1. 3-1. 暦年贈与
- 3.2. 3-2. 相続時精算課税制度
- 3.3. 3-3. 特別控除を使った贈与
- 4. 4. 生前贈与を行う際の注意点
- 4.1. 4-1. 贈与時期に気をつける
- 4.2. 4-2. 暦年贈与の持ち戻し期間
- 4.3. 4-3. 贈与契約書を作成する
- 4.4. 4-4. 専門家に相談する
- 5. 5. まとめ
1. 生前贈与とは?4つの贈与方法の中の1つ
生前贈与とは、人が生きているうちに自分の財産を他人に無償で譲り渡すことです。法律では、贈与には大きく分けて4種類あります。
生前贈与、 遺贈、 死因贈与、 負担付贈与
この中で、今回は生前贈与に焦点を当てて説明します。生前贈与は、他の3つと違い、贈与する人(贈与者)が存命中に行われる贈与です。つまり、まだお元気なうちに、自分の意思で大切な人に財産を渡すことができるのです。 生前贈与は、相続税対策としてよく利用されます。
なぜなら、生前に財産を分けることで、将来の相続財産を減らすことができるからです。
ただし、むやみに行うと思わぬトラブルを招くこともあります。正しい知識を持って行うことが大切です。
2. 生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与には、いくつかのメリットとデメリットがあります。ここでは主なものを紹介します。
2-1. メリット:相続税の節税になる
生前贈与の最大のメリットは、相続税の節税対策になることです。
相続税は、亡くなった人の財産が一定額を超えると課税されます。しかし、生前贈与を利用すれば、相続財産を減らすことができるので、
結果的に相続税を抑えられる可能性があります。
例えば、毎年110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからないという制度があります。
これを利用して計画的に財産を移すことで、将来の相続税を軽減できるのです。
2-2. メリット:早めに財産を渡せる
生前贈与のもう一つの大きなメリットは、子どもや孫など、大切な人に早めに財産を渡せることです。
例えば、お孫さんの教育資金や、お子さんの住宅購入資金として活用できます。
受け取る側にとっても、必要なタイミングで財産をもらえるのはありがたいものです。家族の絆を深める良い機会にもなるでしょう。
2-3. デメリット:贈与税がかかる可能性がある
一方で、生前贈与にはデメリットもあります。その一つが、贈与税がかかる可能性があることです。
先ほど、年間110万円以下の贈与は非課税だと説明しました。しかし、それを超える贈与を行うと、贈与税が課税されます。
贈与税は相続税よりも税率が高いので、場合によっては相続税よりも多く税金を払うことになるかもしれません。また、贈与した財産の管理や、家族間のトラブルなども気をつけるべき点です。
3. 生前贈与の種類と特徴
生前贈与には、いくつかの種類があります。ここでは主なものを3つ紹介します。
3-1. 暦年贈与
暦年贈与とは、毎年110万円までの贈与を非課税で行える制度です。
1月1日から12月31日までの1年間に、1人の人に対して110万円まで贈与できます。
この制度は、誰でも利用できるため、多くの人が相続税対策に活用しています。ただし、110万円を超えると贈与税がかかるので注意が必要です。また、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
3-2. 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子や孫への贈与に使える制度です。2,500万円まで非課税で贈与でき、将来相続が発生した時に精算する仕組みです。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
この制度は一度選択すると取り消せないので、よく考えて利用する必要があります。
また、2,500万円を超える部分には一律20%の税金がかかります。
3-3. 特別控除を使った贈与
特別控除を使った贈与には、以下のようなものがあります:
- 教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税)
- 結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税)
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)(最大2000万円まで非課税、持ち戻し無し)
これらは特定の目的のための贈与に対して、大きな非課税枠が設けられています。
ただし、それぞれ細かい条件があるので、利用する際は注意が必要です。
4. 生前贈与を行う際の注意点
生前贈与を行う際には、いくつか注意すべき点があります。ここでは3つの重要なポイントを紹介します。
4-1. 贈与時期に気をつける
贈与の時期は非常に重要です。特に注意すべきは、相続開始前3年以内の贈与です。(令和6年現在)
この期間内の贈与は、相続財産(みなし贈与)に加算されてしまいます。つまり、相続税の節税効果が薄れてしまうのです。 計画的に早めから贈与を始めることで、この問題を避けることができます。
4-2. 暦年贈与の持ち戻し期間
持ち戻し期間が3年から7年になるのは2024年1月1日以後の贈与が対象になります。
過去の贈与にまで遡って7年になるわけではありません。
例えば、2028年1月1日に亡くなった場合、2024年1月1日~2028年1月1日までの4年間が対象になります。逆に2026年1月1日に亡くなった場合は、従来通り3年間が対象となります。
実際に7年間の持ち戻し加算期間に完全に移行されるのは、2031年1月1日以降です。
例えば2031年5月1日に亡くなった場合、過去3年間分は相続財産に加算され、4年〜7年は100万円を控除した残りの贈与分が加算されることになります。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日まで |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内 |
4-3. 贈与契約書を作成する
生前贈与を行う際は、必ず贈与契約書を作成しましょう。これは、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。 贈与契約書には、贈与の日付、贈与者と受贈者の名前、贈与する財産の内容などを明確に記載します。できれば公正証書にすることをお勧めします。
4-4. 専門家に相談する
生前贈与は税金や法律に関わる複雑な問題です。自分で判断するのは難しいことも多いでしょう。
そのため、安易にご自身で進めず税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
専門家のアドバイスを受けることで、自分の状況に最適な贈与の方法を選んだり、思わぬ落とし穴を避けたりすることができます。
当事務所にご相談いただいた場合にも、相続に強い税理士または弁護士にサポートを依頼しています。
5. まとめ
生前贈与は、相続税対策や家族への財産移転の手段として有効な方法です。しかし、メリットだけでなくデメリットもあり、また複雑な規則もあります。 大切なのは、自分の状況をよく理解し、計画的に行うことです。また、専門家のアドバイスを受けることも重要です。 生前贈与を上手に活用することで、ご自身の老後の安心と、大切な家族の幸せにつながることでしょう。ぜひ、この記事を参考に、ご自身に合った生前贈与の方法を考えてみてください。