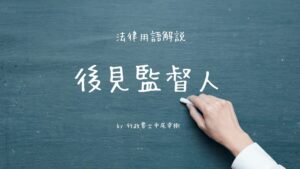家族信託が有効なケース1

佐藤家の日曜日の朝。リビングには父の健太郎(65歳)、母の美智子(62歳)、長男の太郎(35歳)、長女の花子(32歳)が集まっています。

健太郎:「みんな、今日は大切な話があるんだ。最近、家族信託というものを知ったんだが、これが我が家の将来に役立つかもしれない。」
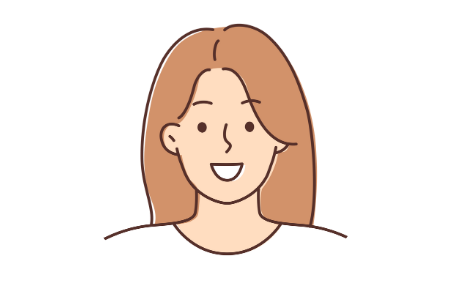
美智子:「家族信託?それって何なの?」

健太郎:「簡単に言えば、家族の中で信頼できる人に財産の管理を任せる仕組みだよ。例えば、私たちが年を取って判断力が低下した時に、子供たちに財産管理を任せられるんだ。」

太郎:「へぇ、それって遺言みたいなものですか?」

健太郎:「似ているけど、遺言よりも柔軟性があるんだ。遺言は亡くなった後にしか効力を持たないけど、家族信託は生きているうちから効果があるんだよ。」
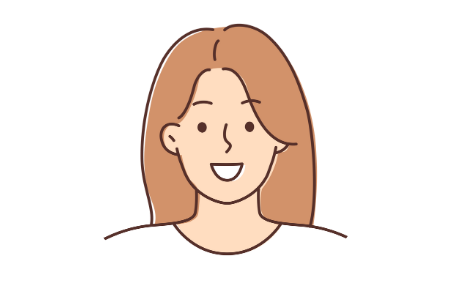
花子:「具体的にはどんなメリットがあるの?」

健太郎:「例えば、私や母さんが認知症になった場合でも、太郎や花子に財産管理を任せられる。これなら、急に判断力が低下しても、家族が速やかに対応できるんだ。」

美智子:「それは安心ね。でも、遺言も大切だと聞くわ。」

健太郎:「その通りだよ。実は、家族信託と遺言を組み合わせると、さらに効果的なんだ。信託で生前の管理を任せつつ、遺言で相続の細かい希望を伝えられる。二つを上手く使えば、家族の絆を守りながら、将来の不安も減らせるんだ。」
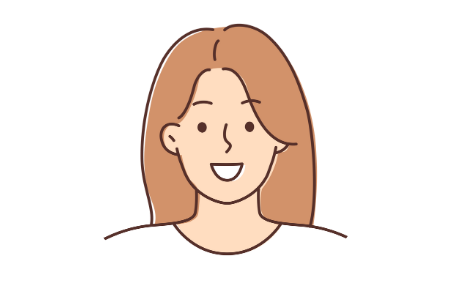
花子:「私たち家族なら、きっと上手くいくわ。でも、どうやって始めればいいの?」

健太郎:「まずは、家族で十分に話し合うことが大切だね。そして、専門家に相談するのがいいだろう。家族信託の設計は、それぞれの家庭に合わせてカスタマイズできるんだ。」家族信託は、単なる財産管理の仕組みじゃない。家族の絆を次の世代に引き継ぐ方法でもあるんだ。」
「家族の絆を未来へ - 佐藤家が選んだ家族信託」
佐藤健太郎さん(65歳)は、最近仕事のストレスから体調を崩すことが増え、将来の健康不安を感じていました。マイホームと貸しビル、そして退職金を含む預貯金がある健太郎さんは、家族の将来を守るため家族信託の活用を決意しました。
佐藤家のケース:家族信託で実現する安心の老後
健太郎さんは自身が委託者となり、長男の太郎さん(35歳)を受託者に指名しました。信託財産には、自宅の一軒家、都心の貸しビル1棟、そして預貯金の大半が含まれます。当初の受益者は健太郎さん夫妻で、万が一の際には妻の美智子さん(62歳)が単独の受益者となる設計です。
家族信託の主な目的
突然の判断能力低下に備えた資産管理
健太郎さんの体調が悪化し判断能力が低下しても、太郎さんが適切に資産を管理できます。例えば、貸しビルのテナント契約や大規模修繕の判断も、太郎さんが行えるようになります。
両親の生活資金の確保
信託財産からの収入(貸しビルの賃料など)は、健太郎さん夫妻の生活費に充てられます。太郎さんは、両親の生活状況を見ながら、必要に応じて資金を管理します。
スムーズな相続対策
将来の相続に備え、計画的な資産移転の準備ができます。例えば、貸しビルの相続税対策として、生前から少しずつ資産を移転することも可能です。
家族の精神的・経済的負担軽減
健太郎さんの判断能力が低下しても、太郎さんが法的に資産管理を行えるため、煩雑な手続きを要する成年後見制度を利用する必要がありません。
健太郎さんは、家族信託と併せて遺言書も作成しました。信託に含まれない財産(例:趣味のゴルフ用品コレクション)の分配や、長女の花子さん(32歳)への感謝の気持ちを込めた贈与などの細かい希望を遺言に記しています。
家族信託を始めるにあたり、佐藤家では何度も家族会議を開きました。太郎さんと花子さんは、両親の想いを深く理解し、家族の絆を強めるこの選択に賛同しました。また、専門家のアドバイスも受けながら、佐藤家に最適な信託の形を作り上げていきました。
美智子さんは当初、複雑な仕組みに戸惑いを感じていましたが、家族で話し合いを重ねるうちに、この選択が家族全員の安心につながることを理解しました。特に、自身が単独の受益者となる可能性があることで、将来への不安が大きく軽減されたと感じています。
このケースのように、家族信託は単なる財産管理の手段ではありません。それは、家族の想いをつなぎ、お互いを支え合う心を形にする方法でもあるのです。将来への不安を軽減し、大切な家族の資産を守りながら、穏やかな老後を過ごすための新しい選択肢、それが家族信託なのです。
(注:家族信託の具体的な設計や税務上の取り扱いは、個々の状況により異なります。専門家に相談することをおすすめします。)
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。