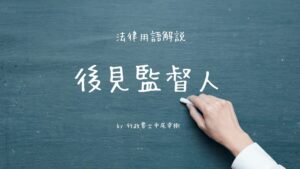「受益者連続型信託とは?具体例で学ぶ柔軟な資産継承の仕組み」

受益者連続型信託という言葉を耳にしたことはありますか?この仕組みは、世代を超えて柔軟に資産を継承できる方法として注目されています。本記事では、受益者連続型信託の基本的な概念と、実際の活用例を紹介します。複雑に思える制度も、具体例を通じて理解することで、自分の家族に適用できるかもしれません。長期的な視点で資産継承を考えたい方は、ぜひ参考にしてください。
受益者連続型信託とは?基本的な仕組みを解説
受益者連続型信託は、複数の世代にわたって計画的に資産を管理・継承するための仕組みです。この制度を理解するには、まず通常の信託との違いを知ることが重要です。
通常の信託との違い
通常の信託では、委託者(資産の所有者)が信託銀行などの受託者に資産を託し、指定された受益者がその利益を受け取ります。一方、受益者連続型信託では、複数の受益者が順次その利益を受け取る点が特徴です。
受益者連続型信託の特徴
受益者連続型信託の主な特徴は以下の通りです:
- 複数の受益者を指定できる
- 受益者の順序を指定できる
- 各受益者の受益期間を設定できる
- 信託財産の管理・処分方法を詳細に定められる
これらの特徴により、長期的かつ柔軟な資産継承が可能になります。
受益者連続型信託の期限について

受益者連続型信託を検討する際に重要な要素の一つが、信託の期限です。この制度特有の期間設定について理解しておくことが、効果的な活用につながります。
法定の信託期間は30年
受益者連続信託は何段階にも受益者を指定できる通常の遺言では叶わない一見、理想的な財産の継承制度ですが無期限にこれを許すことはかえって将来の利害関係人を害することになる懸念があり、信託法91条でその期限は30年と定められています。
この30年の考え方は、信託設定から30年が経過した時に受益者となっていた人の次の新受益者までを限度とするという意味です。30年で強制的に受益権が消滅するわけではありません。
期間設定の考え方
信託期間の設定は、信託の目的や家族の状況に応じて柔軟に行うことができます。以下のような点を考慮して期間を決定するとよいでしょう:
- 資産の性質:不動産や事業用資産など、長期的な管理が必要な資産の場合は、より長い期間設定が適している場合があります。
- 家族の年齢構成:次世代の成長や自立のタイミングを考慮し、それに合わせた期間設定が可能です。
- 目的の達成:例えば、孫の教育資金の確保が目的の場合、孫が成人するまでの期間を設定するなど、具体的な目標に合わせて期間を決めることができます。
- 社会経済の変化:長期にわたる信託の場合、社会経済の変化に対応できるよう、ある程度の柔軟性を持たせることも重要です。
期間設定は、信託の効果を最大限に引き出すための重要な要素です。専門家のアドバイスを受けながら、自分の家族に最適な期間を慎重に検討することをおすすめします。
受益者連続信託の具体的な活用例
受益者連続信託の活用方法をより深く理解するため、具体的な事例を見ていきましょう。
事例1:三世代にわたる資産継承
【設定例】
委託者:70歳の祖父
信託財産:不動産(賃貸マンション)
受託者:信頼のおける親族
受益者順:祖父→子→孫
この例では、祖父が所有する賃貸マンションを信託財産とします。受託者は信頼のおける親族を設定しました。
まず祖父が家賃収入を受け取り、祖父の死後は次男が、その後は孫が受益者となります。各世代の生活状況に応じて、受け取る家賃収入の割合を変えることも可能です。
この方法により、資産が散逸することなく、三世代にわたって安定した収入源を確保することができます。
信託をしていなかった場合には、その都度、遺言または遺産分割協議が行われ最悪の場合には賃貸マンションを売却し分配することが必要になる場合があります。これを防ぐことができる制度が家族信託であり、受益者連続信託の特徴です。
事例2:認知症に備えた資産管理
【設定例】
委託者:65歳の夫婦
信託財産:預金、有価証券
受益者順:夫婦→子供
この例では、夫が健康なうちに資産の一部を子に信託します。夫が受益者である間は、子が受託者として資産の管理をします。このようにしておけば認知症になった場合、夫の口座にある資産は信託財産として既に子の管理下にあるため夫のために使用することができます。例えば、介護費用の支払いや、定期的な生活費の支給などを行えます。(身上監護は信託ではできませんが、実際には認知症になった両親の子であれば契約ができる介護施設も多く存在します。)
夫の死後は妻を第二の受益者とするよう設定し引き続き子が受託者となり受益者のために資産を管理します。妻が亡くなった後には信託契約を終了させるよう設定することで、残った信託資産を継承することができます。。このように、認知症になった後の資産管理の不安を解消しつつ、次世代への継承も実現できます。
事例3:家族経営の事業承継
【設定例】
委託者:60歳の社長(父)
信託財産:自社株式
受益者順:父→長男(後継者)→次男
家族経営の会社を、スムーズに次世代に引き継ぐ方法として受益者連続型信託を活用できます。この例では、社長である父が自社株式を信託財産とします。
まず父が経営権を維持しつつ、徐々に長男に経営を移行していきます。父の引退後は長男が経営権を取得し、会社の利益を受け取ります。長男が経営者として不適格となった場合や、突然の事故などに備えて、次の受益者として次男を指定することも可能です。
この方法により、計画的な事業承継と、不測の事態への対応を同時に実現できます。
受益者連続型信託のメリットとデメリット
受益者連続型信託には多くのメリットがありますが、同時に考慮すべき点もあります。
長期的な資産管理のメリット
- 世代を超えた計画的な資産継承が可能
- 委託者の意思を長期にわたって反映できる
- 家族の状況変化に応じた柔軟な設計ができる
- 認知症などの不測の事態にも対応できる
考慮すべき課題と対策
- 設定の複雑さ:専門家のアドバイスを受けることが重要
- 長期的な拘束:ある程度の柔軟性を持たせた設計が必要
- 受益者間の利害対立:公平性を考慮した設計と、家族間での十分な話し合いが大切
まとめ
受益者連続型信託は、世代を超えた柔軟な資産継承を可能にする仕組みです。具体的な活用例を見てきたように、家族の状況や目的に応じて様々な設計ができます。長期的な視点で資産管理を考えたい方、家族の将来に備えたい方にとって、有効な選択肢の一つとなるでしょう。
ただし、その設定には専門的な知識が必要です。興味を持たれた方は、まずは行政書士や弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。家族の未来を見据えた最適な資産継承の方法を、じっくり検討してみてはいかがでしょうか。
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。