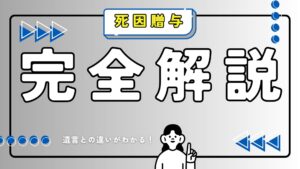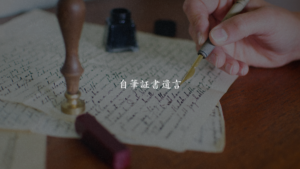「遺言書の検認」知らないと損する重要手続き

- . 「遺言書の検認」知らないと損する重要手続き
- 1. 遺言書の検認とは?その重要性と必要性
- 1.1. 検認の意味と役割:家庭裁判所による確認手続き
- 1.2. 検認を怠るとどうなる!?相続トラブルのリスク
- 1.2.1. 遺言書の有効性が疑われる
- 1.2.2. 相続人間のトラブル
- 1.2.3. 相続手続きの長期
- 1.2.4. 財産分割の困難
- 1.2.5. 法的効力の問題
- 2. 遺言書の検認手続きの流れと注意点
- 2.1. 自筆証書遺言と公正証書遺言:検認の違い
- 2.2. 2020年法改正:自筆証書遺言の保管制度について
- 3. 検認必須!銀行と不動産登記の相続手続き
- 3.1. 銀行での相続手続き:検認済み遺言書の重要性
- 3.2. 不動産の相続登記:検認と登記手続きの関係
- 4. まとめ
遺言書の検認とは?その重要性と必要性
遺言書の検認とは、遺言書の形式的な有効性を家庭裁判所が確認する手続きです。多くの方が「遺言書を作成すれば十分」と考えがちですが、実はその後の検認手続きが非常に重要なのです。
検認には主に二つの目的があります。
一つは、遺言書の存在と内容を公的に証明すること。
もう一つは、遺言書の形式的な有効性を確認することです。
これにより、相続人全員が遺言の内容を確実に知ることができ、遺言書の偽造や変造を防ぐことができます。
特に自筆証書遺言の場合、検認は必須の手続きとなります。
なぜなら、自筆証書遺言は個人が作成するため、その真正性を確認する必要があるからです。
一方、公正証書遺言の場合は、公証人の関与により作成時点で一定の信頼性が担保されているため、原則として検認は不要です。
検認の意味と役割:家庭裁判所による確認手続き
検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を保管し、相続人全員に遺言書の内容を開示します。具体的には、以下のような流れで進みます:
遺言書の所持者が家庭裁判所に検認の申立てを行う
家庭裁判所が期日を指定し、相続人全員を呼び出す
指定された日時に、裁判官立ち会いのもと遺言書を開封
裁判官が遺言書の形式的要件を確認
相続人全員に遺言書の内容を開示
この過程で、遺言書の存在と内容が公的に証明され、相続人全員がその内容を確実に知ることができます。また、裁判官が遺言書の形式的要件を確認することで、遺言の有効性に関する基本的な問題点を早期に発見することができます。
検認を怠るとどうなる!?相続トラブルのリスク
検認を怠ると、様々なリスクが生じる可能性があります。主なリスクとしては以下のようなものが挙げられます:
遺言書の有効性が疑われる
検認を経ていない遺言書は、その存在や内容に疑いが生じやすくなります。
相続人間のトラブル
遺言書の内容を知らなかった相続人が、後になって異議を唱える可能性があります。
相続手続きの長期
検認を経ていないことで、相続手続きが滞り、解決までに時間がかかる可能性があります。
財産分割の困難
遺言書の内容に基づいた財産分割が円滑に進まず、相続人間の対立が深刻化する恐れがあります。
法的効力の問題
検認を経ていない自筆証書遺言は、法的に無効となる可能性があります。
これらのリスクを回避し、遺言者の意思を確実に実現するためにも、検認手続きは非常に重要なのです。
遺言書の検認手続きの流れと注意点
検認手続きの基本的な流れは先ほど説明した通りですが、ここではより詳細に、注意点を交えて解説します。
- 検認の申立て
- 遺言書の所持者(遺言書を保管している人)が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立人は、相続人や受遺者でなくても構いません。
- 必要書類の準備
- 戸籍謄本、遺言書の写し、申立書などの書類を準備します。必要書類は裁判所によって若干異なる場合があるので、事前に確認しましょう。
- 期日の指定
- 裁判所が検認の期日を指定し、相続人全員に通知します。
- 検認期日の出頭
- 指定された日時に、相続人全員が裁判所に出頭します。都合がつかない場合は、委任状を提出することで代理人の出席も可能です。
- 遺言書の開封と確認
- 裁判官立ち会いのもと、遺言書が開封され、内容が確認されます。
- 検認調書の作成
- 裁判所が検認調書を作成し、これにより検認手続きが完了します。
注意点としては、検認はあくまで形式的な確認手続きであり、遺言の内容の妥当性や効力を判断するものではないことです。また、相続人全員の立ち会いが原則ですが、正当な理由がある場合は欠席も認められます。
自筆証書遺言と公正証書遺言:検認の違い
自筆証書遺言と公正証書遺言では、検認の必要性が異なります。
自筆証書遺言
- 検認が必須
- 相続人全員の立ち会いが原則必要
- 遺言書の形式的要件(自筆であること、日付の記載、署名・押印があることなど)を確認
公正証書遺言
- 原則として検認不要
- 公証人の関与により、作成時点で一定の信頼性が担保されている
- ただし、相続人が遺言内容を確認したい場合は、公証役場で閲覧可能
自筆証書遺言は作成が簡単である一方、検認手続きが必要となります。公正証書遺言は作成時に手間と費用がかかりますが、検認が不要で相続手続きがスムーズに進みやすいというメリットがあります。
2020年法改正:自筆証書遺言の保管制度について
2020年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。この制度を利用すると、以下のようなメリットがあります:
- 遺言書の紛失や隠匿のリスクが軽減される
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 遺言書の存在が相続人全員に通知される
保管制度を利用するには、法務局に遺言書を持参し、所定の手続きを行います。
保管手数料は3,900円で、遺言者の生存中はいつでも撤回や変更が可能です。
この制度により、自筆証書遺言の利便性が向上し、より多くの方が安心して遺言を残せるようになりました。ただし、この制度を利用しても、遺言の効力や内容の有効性を法務局が確認するわけではないので、作成時には十分な注意が必要です。
以上が、遺言書の検認手続きの流れと注意点、そして関連する最新の制度についての説明です。次の見出しでは、検認後の相続手続きについて解説していきます。
合わせて読みたい
公正証書遺言の基礎知識
【必読】公正証書遺言の基礎知識:作成手順から費用まで徹底解説 「遺言書を作ろうと思っても、何から始めればいいのかわからない…。そんな悩みを抱えている60代~80代の夫婦は多いのではないでしょうか。実は、遺言書には公正証書 […]
検認必須!銀行と不動産登記の相続手続き
検認手続きを経ていないと進められない重要な相続手続きがあります。
特に注意が必要なのは、銀行での相続手続きと不動産の相続登記です。これらについて詳しく説明します。

銀行での相続手続き:検認済み遺言書の重要性
銀行での相続手続きには、検認済みの遺言書が必要不可欠です。
- 銀行の要求:多くの銀行は、自筆証書遺言の場合、検認済みであることを確認できる書類(検認調書など)の提出を求めます。
- 手続きの流れ:
- 検認済み遺言書と必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)を銀行に提出
- 銀行が遺言書の内容を確認
- 遺言書に基づいて預金の払い戻しや名義変更を実施
- 検認がない場合のリスク:検認を経ていない遺言書では、銀行が相続手続きを受け付けない可能性があります。これにより、預金の払い戻しや名義変更が大幅に遅れる恐れがあります。事実上、検認済み遺言書の提出が条件だと言えます。
不動産の相続登記:検認と登記手続きの関係
不動産の相続登記においても、自筆証書遺言の場合は検認が必須となります。
- 法務局の要求:法務局は、自筆証書遺言に基づく相続登記申請の際、検認済みであることを証明する書類(検認調書の謄本など)の提出を求めます。それがない場合による相続による所有権移転登記申請は却下するという取り扱いがあります。(平7・12・4民三4343)
- 登記手続きの流れ:
- 検認済み遺言書と必要書類(戸籍謄本、固定資産評価証明書など)を準備
- 司法書士に依頼するか、自分で法務局に登記申請
- 法務局が書類を審査し、問題がなければ登記完了
- 検認がない場合の影響:検認を経ていない遺言書では、相続登記が受理されません。これにより、不動産の名義変更が滞り、売却や賃貸などの取引に支障をきたす可能性があります。
以上の点から、遺言書の検認は単なる形式的な手続きではなく、実際の相続手続きを進める上で極めて重要であることがわかります。銀行での手続きや不動産の相続登記をスムーズに行うためにも、遺言書の検認を適切に行うことが不可欠です。
検認手続きを怠ると、相続手続き全体が滞る可能性があるため、遺言書作成後は速やかに検認手続きを進めることをお勧めします。また、これらの手続きについて不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、円滑な相続手続きを進めることができます。
まとめ
遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の形式的な有効性を確認する重要な手続きです。特に自筆証書遺言では必須となります。検認により、遺言書の存在と内容が公的に証明され、相続人全員がその内容を確実に知ることができます。検認を怠ると、遺言書の有効性が疑われたり、相続人間のトラブルが発生したりするリスクがあります。
また、銀行での相続手続きや不動産の相続登記には、検認済みの遺言書が必要不可欠です。検認がない場合、これらの重要な相続手続きが進められず、財産の移転が大幅に遅れる可能性があります。
2020年から始まった自筆証書遺言の保管制度も、検認手続きの簡素化に寄与しています。遺言書作成後は速やかに検認手続きを進めることが、円滑な相続のために重要です。
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。