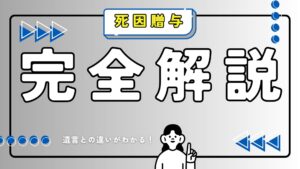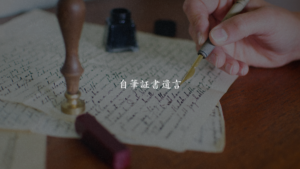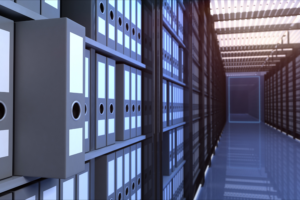【必読】公正証書遺言の基礎知識:作成手順から費用まで徹底解説

「遺言書を作ろうと思っても、何から始めればいいのかわからない…。そんな悩みを抱えている60代~80代の夫婦は多いのではないでしょうか。実は、遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があり、メリット・デメリットがそれぞれ異なります。この記事では、公正証書遺言についての基礎知識から、作成手順、費用、ベストタイミングまで徹底解説。遺言書の作成は、残された家族への大切な贈り物。ぜひ、この記事を参考に、安心して人生の締めくくりを迎えられる準備を始めてみませんか?」
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、公証人の関与により法的効力が高く、内容の正確性も担保されるため、法的トラブルのリスクを避けられます。また、遺言内容についても公証人から適切なアドバイスがもらえるので、自分の想いを正確に伝えられるのが大きな魅力です。
公正証書遺言のメリットをまとめると、以下の3つが挙げられます。
- 法的効力が高く、作成した遺言が無効になるリスクを避けられる
- 公証人からのアドバイスにより自分の想いを正確に遺せる
- 遺言書の自署が不要
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 紛失や改ざん、隠匿、破棄といった自筆証書遺言にありがちなトラブルを確実に避けることができる
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて安全確実な遺言方法です。公証人は法曹資格者や法律事務の経験者であり、正確な法律知識と豊富な実務経験を有しているため、複雑な内容でも法律的に整理した遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言では、体力低下や病気で手書きが困難な場合は作成できませんが、公正証書遺言では署名や押印ができなくても公証人が対応することで遺言が可能です。また、公証人が出張して遺言書を作成することもできます。(別途費用がかかる)
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が不要で、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。さらに、日本公証人連合会の二重保存システムや遺言情報管理システムにより、記録保管や遺言の有無の確認も安心して行えます。
以上のように、公正証書遺言は、公証人の専門性と柔軟な対応、確実な保管と管理により、安全で確実な遺言方法といえるでしょう。
自筆証書遺言のデメリット
一方、自筆証書遺言は費用がかからず簡単に作成できますが、書き方を間違えると無効になるリスクがあります。また、遺言内容について専門家のアドバイスがないため、自分の想いが正確に伝わらない可能性もあります。
自筆証書遺言のデメリットをまとめると、以下の3つが挙げられます。
- 書き方を間違えると無効になるリスクがある
- 専門家のアドバイスがないため、自分の想いが正確に伝わらない可能性がある
- 紛失や改ざんのリスクがある
特に、法律知識が乏しい場合、自筆証書遺言を選ぶことで、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
以上のことから、多くの専門家は、公正証書遺言を推奨しています。公正証書遺言なら、法的効力が高く、内容の正確性も担保されるため、安心して遺言を残すことができるからです。
公正証書遺言の作成手順
公証役場への予約
公正証書遺言をご自身で作成するには、まず公証役場に予約を取ります。公証役場は全国にあり、予約方法は公証役場によって異なります。電話やメールで予約を取れる場合もあれば、直接公証役場に出向く必要がある場合もあります。
予約の際は、以下の点に注意しましょう。
- 遺言者本人または親族等が公証役場に連絡を入れ予約を取る
- 予約の際に、遺言者の氏名、住所、生年月日、電話番号などを伝えること
- 遺言内容について、ある程度まとめておくこと
特に、遺言内容についてはある程度まとめておくことが大切です。特に特定の一人に対する相続や、遺留分を侵害する内容、または相続人以外の第三者への遺贈をする場合には後のトラブルを避けるためにもよく遺言の内容を考えておきましょう。
遺言内容の整理と必要書類の準備
予約が取れたら、次は遺言内容の整理と必要書類の準備です。遺言内容は、できるだけ具体的に整理しましょう。特に、以下の点には注意が必要です。
公正証書遺言を作成する際に準備する書類:
遺言者本人の身分証明
- 3か月以内に発行された印鑑登録証明書
- または官公署発行の顔写真付き身分証明書
遺言者と相続人との続柄確認
- 戸籍謄本や除籍謄本
相続人以外への遺贈の場合
- 遺贈先の個人:住所が分かる住民票やハガキ等
- 遺贈先の法人:登記事項証明書または代表者事項証明書
不動産の相続
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書
預貯金等の相続
- 預貯金通帳またはそのコピー
証人を遺言者が用意する場合
- 証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業を記したメモ
以上の書類を事前に準備することで、スムーズに公正証書遺言の作成が行えます。
遺言原案の作成まで
遺言者は相続内容のメモを用意します。このメモには、遺言者が所有する財産の内容、相続人や遺贈先の詳細、それぞれの相続割合などを記載します。できあがったメモは、メール、ファックス、郵送、直接持参などの方法で公証人に提出します。あわせて、事前に準備した必要書類も公証人に提出してください。
次に、公証人はメモと必要書類を基に遺言公正証書の案を作成し、メール等で遺言者に送付します。遺言者は内容を確認し、修正したい点があれば公証人に伝えます。公証人は遺言者の指示に従って案を修正し、最終的な遺言公正証書を完成させます。
このように、遺言者と公証人が協力して遺言公正証書(案)を作り上げていきます。
遺言作成日の確定と作成日当日の流れ
まず、遺言公正証書の案が確定したら、公証人と遺言者等で打ち合わせを行い、遺言者が公証役場に出向くか、公証人が遺言者の自宅や病院等に出張するかを決めます。そして、公正証書遺言を行う日時を確定します。
遺言当日、遺言者は証人2名の前で公証人に遺言内容を口頭で告げます。公証人は遺言者の判断能力と真意を確認した上で、事前に準備した遺言公正証書の原本を、遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させ、内容に間違いがないことを確認してもらいます。必要に応じてその場で修正を行います。
内容に誤りがなければ、遺言者と証人2名が遺言公正証書の原本に署名・押印します。最後に公証人が署名と職印の押捺を行い、遺言公正証書が完成します。なお、遺言者が自由に真意を述べられるよう、利害関係人には席を外してもらうのが一般的です。
以上のように、公証人立会いのもと、遺言者と証人が遺言内容を確認し、署名・押印することで、遺言公正証書が正式に作成されます。
公正証書遺言の作成にかかる時間と費用
作成にかかる時間
公正証書遺言の作成には、予約から完成まで、通常1~2ヶ月程度の時間がかかります。ただし、遺言内容が複雑な場合や、必要書類の準備に時間がかかる場合は、さらに時間がかかることもあります。
スムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。
- 早めに公証役場に予約を取る
- 遺言内容をできるだけ具体的に整理しておく
- 必要書類は事前に準備しておく
特に、遺言内容については、家族とよく話し合い、納得のいくものにしておくことが大切です。
作成にかかる費用
公正証書遺言の作成費用は、その相続財産の額や相続人の数によって異なりますが、通常5~20万円程度です。費用の内訳は、以下のようになっています。
- 公証人手数料
- 謄本・抄本費用
ただし、この費用は、相続財産の価値に比べれば決して高くはありません。むしろ、公正証書遺言を作成することで、相続トラブルを防ぎ、家族の平和を守ることができると考えれば、必要な投資だと言えるでしょう。費用についてはこちらに詳しく掲載しておりますので、ご参照ください。
公証人手数料
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。
公証役場での相談は無料ですが、遺言の目的財産の額に応じで、次の通り手数料の定めがあります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5,000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5,000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
遺言公正証書の手数料の算出方法と留意点は以下の通りです。
- 相続人や受遺者ごとに財産の価額を算出し、基準表に当てはめて手数料を求め、それらを合算します。
- 財産が1億円以下の場合は、算出された手数料に1万1000円の「遺言加算」が加算されます。
- 原本、正本、謄本の作成や交付にも手数料が必要です。原本は4枚(横書きの場合は3枚)を超える分について1枚250円、正本と謄本は1枚250円の手数料が加算されます。
- 病床での作成の場合は手数料が50%加算され、公証人が出張する場合は日当と交通費が必要です。
- 具体的な手数料の算定には、他にも考慮すべき点があるため、詳細は各公証役場にお問い合わせください。
遺言公正証書の手数料は、相続財産の額や作成状況によって変動します。基本的な算出方法を理解した上で、追加費用も考慮し、公証役場に相談することが大切です。
日本公証人連合会_遺言 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
遺言書作成のベストタイミング
元気なうちに準備を始める
公正証書遺言の作成は、元気なうちに始めることが大切です。特に、以下のようなタイミングが適しています。
- 定年退職後
- 子どもの独立後
- 健康診断で異常が見つかったとき
ただし、具体的なタイミングは人それぞれです。大切なのは、「遺言書を作ろう」と決意したら、できるだけ早く行動に移すことです。
家族の関係が良好であっても遺言作成は必要
遺言書の作成は、家族との話し合いをすることでいい方向に向かうこともありますが、逆にそうでない場合もあります。遺言で相続財産の配分先を決めることで家族の対立が生まれてしまうことも。唯一言えることは、たとえ家族間の関係が良好であったとしても遺言を作成しておく方が良いということでしょう。相続時には相続人でない第三者、主に相続人の配偶者らが相続について口を出してしまうことで紛糾する場面が想定されるためです。
- 相続人の範囲
- 相続財産の分け方
- 遺言執行者の選定
- 葬儀や埋葬に関する希望
家族で遺言について話し合うことで、お互いの想いを共有し、納得のいく遺言内容を決めることができるでしょう。
まとめ:安心して人生の締めくくりを迎えるために
遺言書の作成は、残された家族への想いを伝える大切な手段です。特に、公正証書遺言は、法的効力が高く、内容の正確性も担保されるため、安心して遺言を残すことができます。
公正証書遺言の作成は、難しいものではありません。大切なのは、「遺言書を作ろう」と決意したら、できるだけ早く行動に移すことです。
- まずは公証役場に予約を取る
- 遺言内容を整理して必要書類を準備する
- 納得のいく遺言内容を決める
この3つを心がければ、スムーズに公正証書遺言を作成できるはずです。
人生の締めくくりに、家族への想いを遺言として残す。それは、残された家族への最高の贈り物になるでしょう。ぜひ、公正証書遺言の作成を検討してみてください。
当事務所では公正証書遺言の作成をサポートする業務を専門としております。
この記事をお読みになり不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちの仕事はあなたの負担を軽くするだけでなく将来における安心をお約束します。
あわせて読みたい
お問い合わせ
CONTACT
わからないことや気になることは、なんでもお気軽にご相談ください。相談やお見積もりは無料です。
お電話のお問い合わせ
営業時間:09:00~18:00
メールのお問い合わせ
お取り扱い地域

神奈川県
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
東京都、埼玉県、千葉県、山梨県等近隣都県も対応可能です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。