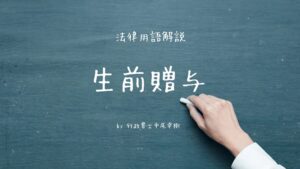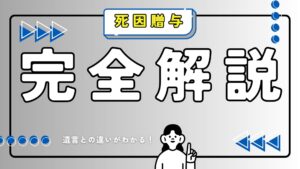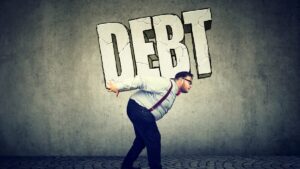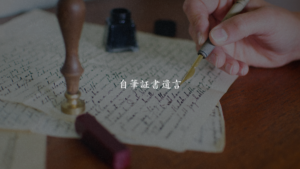遺言書を作成しても、それを確実に実行するための鍵を握っているのが遺言執行人です。信頼できる人を選びしっかりと引き継ぎをしておかないと、せっかくの遺言が意味をなさなくなってしまうこともあります。万が一に備えて、遺言執行人の選び方と、スムーズな遺言執行のための事前準備について知っておきましょう。遺言執行人を適切に選定し、必要な取り決めを済ませておけば、残される家族も安心です。今回は、遺言執行人の重要性から選定のポイント、事前の準備や引き継ぎまで、詳しく解説します。
- 1. 遺言執行人が果たす重要な役割とは
- 1.1. 遺言執行人の職務内容
- 1.2. 遺言執行人に求められる資質
- 1.3. 遺言執行人の法的責任
- 2. 遺言執行人の選び方のポイント
- 2.1. 配偶者や子供を遺言執行人に選ぶメリットとデメリット
- 2.2. 信頼できる親族や友人に依頼する際の注意点
- 2.3. 行政書士などの専門家に依頼するメリット
- 2.4. 複数の遺言執行人を選任する方法
- 2.5. 遺言執行人の選定で失敗しないための心構え
- 3. スムーズな遺言執行のための事前準備
- 3.1. 遺言書の内容を遺言執行人に詳しく説明する
- 3.2. 相続財産や必要書類の所在を伝える
- 3.3. 遺言執行の手続きの流れを確認する
- 3.4. 遺言執行にかかる費用と報酬を取り決める
- 3.5. 遺言執行後の関係性についても話し合う
- 4. トラブルを避けるための遺言執行人との上手な付き合い方
- 4.1. 定期的な連絡を取り、状況を共有する
- 4.2. 感謝の気持ちを伝える
- 4.3. 遺言執行人の判断を尊重する
- 5. まとめ:万が一に備えて今から始める遺言執行人選び
遺言執行人が果たす重要な役割とは
遺言執行人は、遺言者が亡くなった後、その遺言の内容を実現するための重要な役割を担います。遺言執行人の主な職務は、
- 遺言の内容を確認
- 相続財産の保全
- 相続財産の調査や確定
- 相続人への遺産分配
- 各種手続きの代行
などを行うことです。
法律上の権限と義務を持ち、遺言者の意思を尊重しながら、公平公正に職務を遂行することが求められます。
遺言執行人の職務内容
遺言執行人の具体的な職務内容は以下のようのものがあります。
- 遺言書の確認と検認手続き:遺言書の存在を家庭裁判所に報告し、検認(確認)の手続きを行います。
- 相続財産の保全:遺言執行者は非常に強い権限を持つと共に、*善管注意義務という大きな責任を負います。
- 相続財産の調査と確定:預貯金や不動産、有価証券などの相続財産を調査し、財産目録を作成。相続人へ配布します。
- 遺言の内容に沿って各相続人に遺産を引き渡す。動産は引き渡し、不動産は登記変更の手続きなど。
- 相続税の申告と納付:相続税の申告期限までに、相続税の申告と納付を行います。(通常は、税理士に依頼することが多い)
- 名義変更など各種手続き:不動産や預貯金、株式などの名義変更手続きを行います。(不動産登記変更は司法書士が行うことが多い)
これらの職務を遂行するためには、遺言の内容を正しく理解し、相続に関する法律知識や事務処理能力が必要とされます。
遺言執行人に求められる資質
遺言執行人には、次のような資質が求められます。
- 誠実で公平公正な人柄:遺言者の意思を尊重し、相続人間の公平性を保てる人物であること。
- 責任感と実行力:法的責任を伴う職務を最後までやり遂げる責任感と実行力を持っていること。
- コミュニケーション能力:相続人や関係機関との円滑なコミュニケーションが取れること。
- 一定の事務処理能力:相続手続きに関する事務処理を滞りなく行える能力があること。
遺言執行人は単なる事務的な役割だけでなく、遺言者との信頼関係に基づく重要な責務を負っています。
遺言執行人の法的責任
遺言執行人は、民法上の「委任契約」に基づく善管注意義務を負います。つまり、遺言者から委任された職務を誠実に履行し、遺言の内容に沿って適切に遺産を管理・分配する義務があるのです。この義務に反し、故意または過失によって相続人に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うことがあります。
また、遺言執行人は相続財産の管理に関して、相続人に対する報告義務も負っています。定期的に相続手続きの進捗状況を報告し、関係者間の情報共有を図る必要があります。
遺言執行人の選び方のポイント
では、具体的にどのような人を遺言執行人に選ぶべきでしょうか。以下のポイントを押さえて、適任者を見つけましょう。
配偶者や子供を遺言執行人に選ぶメリットとデメリット
配偶者や成人した子供を遺言執行人に選ぶケースは多いですが、メリット・デメリットがあります。
メリット
- 遺言者の意思をよく理解している
- 相続人との意思疎通がスムーズ
- 報酬を支払う必要がない
デメリット
- 公平性を保つことが難しい
- 感情的になりやすく、トラブルの原因になる
- 事務処理能力が不足している場合がある
近親者に依頼する場合は、メリット・デメリットを十分に考慮し、適任かどうかをよく見極める必要があります。
信頼できる親族や友人に依頼する際の注意点
配偶者や子供以外の親族や友人に遺言執行を依頼する場合は、次の点に注意しましょう。
- 本人の意思を尊重し、強要しない
- 十分な説明を行い、理解と同意を得る
- 公平性を保てる人を選ぶ
- 事前に手続きや報酬について取り決める
親しい間柄だからこそ、きちんと話し合って理解を得ておくことが大切です。
行政書士などの専門家に依頼するメリット
遺言執行手続きに困難が予想される場合や疎遠な相続人へ説明等困難が予想される場合、専門家に依頼するのも一つの方法です。
メリット
- 手続きを正確かつスピーディーに進められる
- 公平中立な立場から職務を遂行できる
- トラブル防止や早期解決が期待できる
デメリット
- 費用がかかる
- 相続人との利害が対立する恐れがある
- 遺言執行人との相性が合わないかもしれない
専門家の起用にはそれなりの報酬がかかりますが、円滑な遺言執行のためには有効な選択肢と言えます。
遺言執行者の義務はあくまで遺言内容の迅速な執行にあります。その為、遺言の内容に不服がある相続人との利害が対立する可能性もありますが、相続人の一人がそれを執り行うよりかは第三者が行った方がスムーズでしょう。
複数の遺言執行人を選任する方法
遺言執行人を複数選任することで、職務の分担や牽制機能を働かせることができます。具体的には、
- 法律専門家と身内を組み合わせる
- 複数の相続人から1名ずつ選任する
- 信頼できる第三者を加える
などの方法があります。各遺言執行人の役割分担を明確にしておくことが、スムーズな連携のポイントです。
しかしながら現実には専門家一名に依頼することを強くおすすめします。
なぜなら、遺言執行者を複数人指定すると、遺言執行者間で意見の対立が発生する可能性があります。そうなると遺言が円滑に行えなくなります。
このような状況を防ぐために、遺言執行者間で意見の対立があった際には、いずれかの特定の遺言執行者の意見に従わせるなど、遺言執行者指定の時点で対策を取ると良いでしょう。
遺言執行人の選定で失敗しないための心構え
遺言執行人選びで最も重要なのは、「適任者を選ぶ」ということです。「頼みやすい人」「断りづらい人」を安易に選んでしまうと、後にトラブルの種になりかねません。
- 信頼関係だけでなく、能力や適性をよく見極める
- 一人に決めつかず、複数の候補者とよく話し合う
- 専門家の意見も参考にする
- 本人の意思を尊重する
客観的な判断を心掛け、十分に時間をかけて選定することが大切です。
スムーズな遺言執行のための事前準備
遺言執行人を決めたら、できるだけ早めに引き継ぎの準備を始めましょう。
遺言書の内容を遺言執行人に詳しく説明する
まずは、遺言書の内容を遺言執行人に隅々まで説明することから始めます。
- 財産の内容や分配方法
- 相続人との関係性
- 想定される課題やトラブル
遺言執行人が遺言者の意思を正確に理解できるよう、丁寧に伝えることが大切です。
相続財産や必要書類の所在を伝える
預貯金通帳、不動産権利証、株券、保険証書など、相続手続きに必要な書類の所在を遺言執行人に伝えておきます。また、金庫の暗証番号や、デジタルデータのパスワードなども共有しておくとスムーズです。
遺言執行の手続きの流れを確認する
遺言執行に必要な一連の手続きについて、遺言執行人と一緒に確認しておくことが大切です。
- 家庭裁判所への検認手続き
- 相続財産の調査と確定
- 遺産分割協議と遺産の引き渡し
- 相続税の申告と納付
- 名義変更などの各種手続き
手続きの流れを把握しておけば、いざという時に慌てずに対応できます。
遺言執行にかかる費用と報酬を取り決める
遺言執行には、一定の費用がかかります。主な内訳は、
- 遺言執行人への報酬(相続人の場合には無償も可能)
- 士業などの専門家への報酬
- 各種手続きの費用(登記費用、郵送料など)
- 相続税
これらの費用については、あらかじめ一定の目安を立て、遺言執行人とよく話し合っておくことが大切です。
特に遺言執行人の報酬については、事前に明確な取り決めを交わしておくことが望ましいです。
遺言執行後の関係性についても話し合う
遺言が執行された後も、遺言執行人を含めた相続人同士の良好な関係性を保つことが理想的です。
- 定期的な連絡や報告の方法
- 感謝の気持ちを伝える機会の設定
- トラブルが発生した際の解決方法
遺言執行後の関係性についても、事前に話し合っておくと安心です。
トラブルを避けるための遺言執行人との上手な付き合い方
せっかく信頼できる遺言執行人を選んでも、相続手続き中にトラブルが発生するケースがあります。それを避けるためには、遺言執行人との上手な付き合い方が欠かせません。
定期的な連絡を取り、状況を共有する
相続手続きの進捗状況について、遺言執行人から定期的に報告を受けるようにしましょう。何か問題が発生していないか、早い段階で察知することが大切です。また、相続人側からも状況を共有し、意思疎通を図ることが信頼関係の維持につながります。
感謝の気持ちを伝える
多忙な中で職務を遂行してくれる遺言執行人に対し、感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。
- 言葉で直接感謝を伝える
- 手紙やメールで気持ちを表す
- 食事や贈り物で感謝を示す
遺言者亡き後も、良好な関係を保てるよう心掛けましょう。
遺言執行人の判断を尊重する
財産の分配方法など、遺言執行人が下した判断について、相続人全員で尊重する姿勢が大切です。たとえ不満があっても、安易に異議を唱えるのは避けましょう。
- 遺言の内容に沿っているか確認する
- 相続人間の公平性が保たれているか見極める
- 疑問点は冷静に話し合う
遺言執行人を信頼し、任せる姿勢を示すことが、円滑な相続手続きにつながります。
まとめ:万が一に備えて今から始める遺言執行人選び
- 遺言執行人は、遺言内容を実現するための重要な役割を担っています。信頼でき、責任感が強く、コミュニケーション能力の高い人を選ぶことが大切です。
- 配偶者や子供、親族や友人、専門家など、幅広い選択肢から適任者を見極める
- 事前の引き継ぎを綿密に行い、遺言の内容や相続財産、必要な手続きを共有しておく
- 遺言執行に必要な費用や報酬についても、あらかじめ明確に取り決めを交わす
- 遺言執行後の関係性についても話し合い、トラブル防止と円滑な相続の実現を目指す
万が一に備えるためには、「備えあれば憂いなし」の精神で、今から遺言執行人選びに着手することが肝要です。信頼できる人を見つけ、十分な時間をかけて引き継ぎを行えば、いざという時も安心して遺言の執行を任せられるはずです。遺言執行人の選定は、単なる事務手続きではなく、「残された家族の幸せを守る大切な備え」だと考えましょう。遺言者の想いを引き継ぎ、相続人の納得と満足が得られるような相続を実現するためにも、適任の遺言執行人を見つけ、しっかりと引き継ぎを行うことを、強くおすすめします。
もちろん、遺言執行人を選んだ後も、常にコミュニケーションを取り、良好な関係性を保つことが大切です。遺言者と相続人、遺言執行人が三位一体となって、円滑な相続の実現を目指しましょう。人生100年時代と言われる今、老後の備えは一日も早く始めることが賢明です。信頼できる遺言執行人選びから始めて、安心で満足のいく相続の実現を目指してみませんか。
お困りごとは三浦市の相続、遺言の専門家である中尾行政書士事務所まで是非お問合せください。
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。