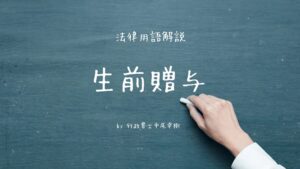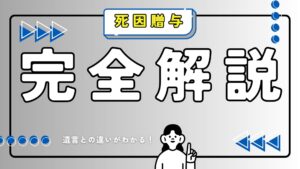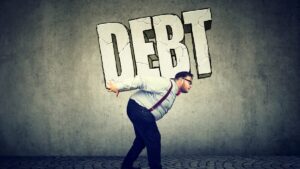大切な家で暮らし続けるために:配偶者居住権の基礎知識
「配偶者が亡くなった後も、長年住み慣れた自宅に住み続けたい」そんな願いを叶える「配偶者居住権」。しかし、その期間や条件について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。本記事では、60代以上の夫婦の皆様に向けて、配偶者居住権の具体的な期間や適用条件を分かりやすく解説します。正確な知識を得ることで、将来の住まいに関する不安を解消し、家族との良好な関係を保ちながら、安心して老後の住まいを計画することができます。配偶者居住権の活用方法から注意点まで、この記事を読めば、あなたの状況に最適な選択ができるようになります。

- 1. 配偶者居住権とは?60代以上の夫婦が知っておくべき基本知識
- 1.1. 財産の評価はどうやって行うの?
- 1.1.1. 配偶者居住権を利用しない場合:
- 1.1.2. 配偶者居住権を利用する場合:
- 2. 配偶者居住権の具体的な期間:いつまで住み続けられる?
- 2.1. 配偶者居住権の適用条件と制限:誰が、どのような場合に利用できるのか
- 3. 配偶者居住権活用方法:メリットとデメリットを徹底解説
- 3.1. 配偶者居住権と相続:子供たちとの関係性を維持しながら権利を行使する方法
- 4. 配偶者居住権の手続きと注意点:スムーズな権利取得のためのステップ
- 4.1. 注意点:
- 4.2. 配偶者居住権の登記:第三者への対抗要件と重要性
- 5. 配偶者短期居住権について
- 6. FAQーよくある質問
- 7. まとめ
- 7.1. 読了後にすべきこと:
配偶者居住権とは?60代以上の夫婦が知っておくべき基本知識
配偶者居住権は、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法で新設された制度です。この制度により、配偶者が亡くなった後も、残された配偶者が生涯にわたって自宅に住み続けることができるようになりました。特に60代以上の夫婦にとって、この制度は老後の住まいに関する大きな安心材料となります。なぜなら、長年住み慣れた自宅で生活を続けられることは、精神的な安定だけでなく、身体的な健康維持にも繋がるからです。
配偶者居住権の最大の特徴は、居住権を相続財産から切り離して考えることができる点です。これにより、自宅を相続する子供たちと、そこに住み続けたい配偶者の利害を調整しやすくなりました。ただし、配偶者居住権にはいくつかの条件や制限があります。例えば、被相続人の所有する建物に相続開始時に居住していることが条件となります。また、この権利は譲渡することができず、賃貸することもできません。
重要な点として、配偶者居住権は令和2年4月1日以降に発生した相続から適用されます。それ以前に亡くなった方の相続では、たとえ遺産分割協議が令和2年4月1日以降であっても、配偶者居住権を設定することはできません。また、亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象とはなりません。この点にも注意が必要です。
配偶者居住権を正しく理解し活用することで、高齢者の皆様は将来の住まいに関する不安を軽減し、より安定した老後生活を送ることができるのです。
財産の評価はどうやって行うの?
配偶者居住権の導入により、遺産分割の方法に大きな変化がもたらされました。具体的な例を用いて、この新しい制度がどのように遺産分割に影響するかを見ていきましょう。
【モデルケース】
遺産総額:6,000万円(自宅4,500万円、預金1,500万円)
相続人:妻(65歳)と長女(40歳)の2人
法定相続分は、妻が1/2、長女が1/2となります。つまり、それぞれ3,000万円ずつ相続することになります。
配偶者居住権を利用しない場合:
妻が4,500万円の自宅を相続すると、長女は1,500万円の預金のみを相続することになります。この場合、長女が平等な分割を望めば、妻は1,500万円を長女に支払う必要があります。しかし、妻にその現金がない場合、自宅を売却せざるを得なくなる可能性があります。また、仮に自宅を相続できたとしても、現金を全て長女が相続しているため、妻は生活資金が不足する恐れがあります。
配偶者居住権を利用する場合:
自宅の評価額4,500万円のうち、配偶者居住権を2,500万円、建物の所有権を2,000万円と仮定します。
この場合、以下のような分割が可能になります:
- 妻:配偶者居住権(2,500万円)+ 預金(500万円) = 3,000万円
- 長女:建物の所有権(2,000万円)+ 預金(1,000万円) = 3,000万円
このように配偶者居住権を活用することで、妻は住み慣れた自宅に住み続けながら、ある程度の生活資金も確保できます。
一方、長女も将来的に建物の所有権を得られるため、バランスの取れた遺産分割が可能になります。
配偶者居住権の評価額は、配偶者の年齢や建物の残存耐用年数などを考慮して算出されます。存続期間は自由に設定できますが、「終身」とすることも可能です。ただし、存続期間が長くなるほど配偶者居住権の評価額は高くなる傾向にあります。また、この評価額算定には税務上、相続法上など非常に難解な計算が必要になるため、相続人間で話がまとまらず評価額の算定を専門家に依頼することになればその費用もかかってくるでしょう。
参考サイト:
国税庁 No.4666 配偶者居住権等の評価
日本不動産鑑定士協会「配偶者居住権等の鑑定評価に関する研究報告」の公表について
法務省 配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)
配偶者居住権の具体的な期間:いつまで住み続けられる?
配偶者居住権の期間について、多くの方が「具体的にどのくらいの期間、住み続けられるのか」という疑問を持っています。結論から言えば、配偶者居住権は原則として終身の権利です。つまり、権利を得た配偶者が亡くなるまで、その住居に住み続けることができます。
ただし、以下のような場合には配偶者居住権が消滅することがあります:
配偶者居住権がなくなる時
- 配偶者が居住建物の占有を失った場合
- 配偶者が第三者に居住建物の占有を移転した場合
- 居住建物が滅失するなどして存在しなくなった場合
- 配偶者が配偶者居住権の放棄を申し出た場合
また、遺産分割協議や遺言により、配偶者居住権の存続期間を定めることも可能です。例えば、「配偶者が80歳になるまで」といった具体的な期限を設けることができます。
このように、配偶者居住権は基本的に生涯にわたって保障されますが、状況に応じて柔軟に期間を設定できる制度となっています。高齢者の方々にとっては、自分の寿命や将来の生活設計に合わせて、適切な期間を選択できることが大きなメリットとなるでしょう。
配偶者居住権の適用条件と制限:誰が、どのような場合に利用できるのか
配偶者居住権を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な適用条件は以下の通りです:
- 被相続人の配偶者であること
- 相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
- 以下のいずれかの方法で配偶者居住権を取得すること:
- 遺産分割
- 遺贈
- 死因贈与
- 家庭裁判所の審判
注意点として、配偶者居住権は特定財産承継遺言(〜を相続させると書く普通の遺言)では設定できません。また、事実婚の場合は適用されないので注意が必要です。
あわせて読みたい
一方で、配偶者居住権には以下のような制限もあります:
- 配偶者居住権は譲渡できない
- 賃貸併用住宅で相続開始時に賃貸中であった部分については配偶者居住権の権利は及びません
- 居住建物の増改築には所有者の承諾が必要
- 通常の必要費(電気代、水道代など)は配偶者が負担
- 大規模修繕費用は原則として所有者(相続人)が負担
これらの制限は、所有者(多くの場合は子供たち)の権利を保護するためのものです。配偶者側がこれらの制限を意図して守らない場合、所有者は配偶者に対してある程度の期間を定めて止めるように伝え、それでも従わない場合には配偶者居住権を消滅させることができます。配偶者側も一定のルールはしっかりと守らないといけませんね。配偶者居住権を行使する際は、これらの制限を理解し、所有者との良好な関係を維持することが重要です。高齢者の方々にとっては、これらの条件と制限を正確に理解することで、自分の状況に配偶者居住権が適用できるかどうかを判断し、将来の住まいについて適切な決定を下すことができます。
配偶者居住権活用方法:メリットとデメリットを徹底解説
配偶者居住権は、高齢者の方々にとって住み慣れた我が家に引き続き無償で住むことができるという非常に有用な制度ですが、活用する際にはそのメリットとデメリットを十分に理解することが重要です。ここでは、配偶者居住権の主なメリットとデメリット、そして効果的な活用方法について解説します。
メリット
- 住み慣れた自宅に無償で住み続けられる
- 配偶者の相続税額の計算において有利に働く場合がある
- 子供たちの相続分を確保しつつ、居住権を保護できる
- 認知症などで判断能力が低下しても、居住権が保護される
デメリット
- 居住建物の譲渡や賃貸ができない
- 通常の必要費(光熱費など)の負担が必要
- 建物の増改築に制限がある
- 配偶者居住権の評価額分だけ相続分が減少する
これらのメリットとデメリットを踏まえ、高齢者の方々が配偶者居住権を効果的に活用するためのポイントは以下の通りです:
- 早めの検討と家族との話し合い:
配偶者の一方が亡くなってからではなく、元気なうちに配偶者居住権について検討し、家族と話し合うことが大切です。 - 財産状況の把握:
自宅の評価額や他の相続財産の状況を把握し、配偶者居住権を設定した場合の相続税や相続分への影響を試算しましょう。 - 長期的な生活設計:
自身の健康状態や将来の介護ニーズなども考慮し、配偶者居住権を活用した長期的な生活設計を行います。 - 専門家への相談:
行政書士や弁護士などの専門家に相談し、自分の状況に最適な配偶者居住権の活用方法を検討しましょう。 - 定期的な見直し:
健康状態や家族関係の変化に応じて、配偶者居住権の設定内容を定期的に見直すことも大切です。
配偶者居住権を上手に活用することで、高齢者の方々は住み慣れた環境で安心して暮らし続けることができます。同時に、子供たちの相続権にも配慮した、バランスの取れた相続対策が可能となるのです。
配偶者居住権と相続:子供たちとの関係性を維持しながら権利を行使する方法
配偶者居住権を行使する際、子供たちとの良好な関係を維持することは非常に重要です。ここでは、配偶者居住権を活用しながら、子供たちとの関係性を保つための具体的な方法を紹介します。
- オープンなコミュニケーション:
配偶者居住権の行使を検討する段階から、子供たちと率直に話し合うことが大切です。親の希望を伝えるとともに、子供たちの意見や懸念にも耳を傾けましょう。 - 公平性の確保:
配偶者居住権を設定することで、居住建物を相続する予定の子供の相続分が減少する可能性があります。他の財産で調整するなど、子供たち全員に対して公平な相続となるよう配慮しましょう。 - 将来の方針の共有:
配偶者居住権の存続期間や、将来的な建物の処分方法などについて、子供たちと一緒に検討し、合意形成を図ります。 - 維持管理の役割分担:
居住建物の修繕や管理について、誰がどのような役割を担うのか、明確にしておきましょう。子供たちの協力を得ることで、負担を分散させることができます。 - 定期的な状況確認:
健康状態や生活状況について、定期的に子供たちと情報共有する機会を設けましょう。必要に応じて、配偶者居住権の内容を見直すことも検討します。 - 専門家の介入:
家族間で意見の相違がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に仲介役を依頼することも有効です。中立的な立場からのアドバイスが、円滑な合意形成につながります。 - 感謝の気持ちを表現:
子供たちの理解と協力に対して、感謝の気持ちを伝えることを忘れずに。良好な関係性を維持するためには、互いの思いやりが不可欠です。
これらの方法を実践することで、配偶者居住権を円滑に行使しながら、子供たちとの絆を深めることができます。高齢者の方々にとって、家族の支えは何よりも大切な財産です。配偶者居住権を家族の理解と協力のもとで活用することで、安心して老後を過ごすことができるでしょう。
配偶者居住権の手続きと注意点:スムーズな権利取得のためのステップ
配偶者居住権を取得するためには、適切な手続きを踏む必要があります。ここでは、スムーズな権利取得のための具体的なステップと注意点を解説します。
- 事前準備:
- 被相続人の死亡診断書を取得する
- 相続人全員の戸籍謄本を収集する
- 居住建物の登記事項証明書を取得する
遺産分割協議:
- 相続人全員で話し合い、配偶者居住権の設定について合意を形成する
- 協議書を作成し、全員が署名・押印する
配偶者居住権の設定:
- 遺産分割協議書に基づき、配偶者居住権を設定する
- 配偶者居住権の存続期間や範囲を明確に定める
登記申請:
- 法務局に配偶者居住権の登記を申請する
- 必要書類:登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票など
税務署への申告:
- 相続税の申告において、配偶者居住権の評価額を適切に計算し申告する
注意点:
- 遺言で配偶者居住権を設定する場合は、公正証書遺言の作成が望ましい
- 配偶者居住権の評価額は、建物の時価や残存耐用年数などから計算される(計算方法の詳しくはこちら)
- 登記を怠ると第三者に対抗できないので、速やかに手続きを行う
- 相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)に注意する
- 令和2年4月1日以降に作成された遺言でなければ、配偶者居住権を遺贈することはできない
配偶者居住権の取得手続きは、法律や税務の専門知識が必要となる場合があります。不安な点がある場合は、弁護士や税理士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。また、高齢者の方々にとっては、これらの手続きが負担になる可能性もあります。子供たちや信頼できる親族の協力を得ながら、慎重かつ確実に手続きを進めることが大切です。配偶者居住権を適切に取得することで、住み慣れた自宅で安心して暮らし続けることができます。手続きの複雑さに躊躇せず、自分の権利を守るために必要なステップを着実に進めていきましょう。
配偶者居住権の登記:第三者への対抗要件と重要性
配偶者居住権は登記をしなくとも住み続ける上では問題ありません。ただそれは配偶者と相続人以外の第三者から見ると配偶者がそこに居住権を持っているとはわかりません。
したがって、「対抗要件」と民法では言いますが、登記をすることで自分たち以外の人に分かるようにしないと、後から善意(そのことについて知らない)の第三者に対抗できず不利益を被る可能性が出てきます。ここでは、配偶者居住権の登記の重要性と、第三者への対抗要件としての役割について詳しく説明します。
- 登記の重要性:
配偶者居住権の登記は、その権利を公に証明する役割を果たします。登記することで、配偶者居住権の存在が誰でも確認できる状態となり、権利の保護が強化されます。 - 第三者への対抗要件:
登記の最も重要な意味は、第三者への対抗要件となることです。対抗要件とは、自分の権利を第三者に主張するために必要な条件のことを指します。
このため、民法では居住建物の所有者となる人に配偶者居住権の登記をさせる義務を負うものと定めています。
第1031条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 e-GOV法令検索
- 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
具体的には以下のような状況で重要となります:
- 相続人が居住建物を他人に売却しようとした場合
- 相続人の債権者が居住建物を差し押さえようとした場合
- 新たな所有者が配偶者に退去を求めてきた場合
これらの状況で、配偶者居住権の登記があれば、「私にはここに住み続ける権利がある」と主張し、権利を守ることができます。また、不動産の登記を備えた後は民法605条4項を準用するので、住居を占有する人に出ていくよう求めることができたり(返還請求)、第三者が住むのを妨害してくるときにはやめさせることができます(妨害停止請求)。
第605条の4
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC605%E6%9D%A1%E3%81%AE2
- その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求
- その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求
- 登記の手続き:
登記は、配偶者居住権が設定されてから可能な限り速やかに行うべきです。手続きは以下の流れとなります:- 必要書類の準備(登記申請書、遺産分割協議書のコピー、戸籍謄本など)
- 法務局への申請
- 登録免許税の納付
- 登記を怠った場合のリスク:
登記を行わないと、以下のようなリスクが生じる可能性があります:- 建物が第三者(善意)に売却された場合、新所有者から退去を求められる
- 相続人の債権者による差し押さえを防げない
- 権利の存在を証明するのが困難になる
- 高齢者の方々への配慮:
登記手続きは専門的で複雑な場合があります。高齢者の方々は、以下の点に注意しましょう:- 子供や信頼できる親族に協力を求める
- 必要に応じて司法書士などの専門家に依頼する
- 手続きにかかる費用(登録免許税など)を事前に確認する
- 定期的な確認:
登記後も、定期的に登記の内容を確認することをお勧めします。特に以下の場合は注意が必要です:- 建物の増改築を行った場合
- 配偶者居住権の内容に変更があった場合
配偶者居住権の登記は、高齢者の方々の居住の安定を守る重要な手段です。「面倒だから」「費用がかかるから」といった理由で登記を怠ると、将来大きな問題に直面する可能性があります。権利を確実に保護するために、必ず登記を行うようにしましょう。
配偶者短期居住権について
配偶者居住権と並んで重要な権利として、「配偶者短期居住権」があります。これは、配偶者居住権が設定されるまでの間、または一定期間、配偶者が居住を継続できる権利です。
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が、亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、以下のいずれか遅い日まで無償で住み続けることができる権利です:
- 遺産分割の協議がまとまるか又は遺産分割の審判がされるまで
- 配偶者の死亡の日から6か月を経過する日
この権利は、配偶者居住権とは異なり、登記をする必要がありません。また、遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合でも、その第三者は配偶者短期居住権を消滅させる申し入れをすることができますが、その場合でも申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
配偶者短期居住権は、遺産分割協議が長引いた場合や、突然の相続で居住の継続が不安定になった場合などに、配偶者の居住を一時的に保護する重要な役割を果たします。
FAQーよくある質問
-
遺言で配偶者居住権を相続させることはできますか?
-
配偶者居住権の取得方法において、注意すべき重要な点があります。いわゆる「相続させる旨の遺言」として知られる特定財産承継遺言は、配偶者居住権を設定する手段としては認められていません。
この規定の背景には、相続人の権利を守る意図があります。もし「相続させる旨の遺言」で配偶者居住権が設定されてしまうと、配偶者がこの権利を望まない場合に問題が生じます。配偶者居住権だけを辞退することができず、相続全体を放棄するという極端な選択をしなければならなくなってしまうからです。
このような状況は、相続人にとって不当に選択の自由を制限することになり、法の趣旨に反すると考えられています。そのため、配偶者居住権の設定には、より柔軟な対応が可能な他の方法が用いられます。これにより、相続人の意思をより尊重した形での権利設定が可能となっているのです。
-
遺言で配偶者居住権を死因贈与を目的としましたが、作成後に全部または一部を第三者に譲渡しました。
-
遺言作成後に色々と状況が変わることはよくあることです。今回の場合には、民法1023条2項により、抵触行為として、遺言者が遺言を撤回したとみなされます。
したがって死後に遺言にその旨が残っていたとしても無効なものとして(撤回したもの)取り扱われます。第1023条【前の遺言と後の遺言との抵触等】
① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1023%E6%9D%A1
-
いらなくなった配偶者居住権を第三者に売って,介護施設に入るための資金を得たいと考えているのですが可能でしょうか?
-
配偶者居住権は、奥様が家に住み続けるための大切な権利です。この権利は人に譲ることはできませんが、放棄して代わりにお金をもらうことはできます。また、家の持ち主さんの許可があれば、その家を人に貸して家賃収入を得ることもできます。
-
被相続人が私たちが住んでいた建物を遺贈していました。直ぐに出ていかなくてはなりませんか?
-
他の相続人に相続、または第三者へ遺贈されていたとしても 「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」 を受けた日から6か月間は,無償で建物に住み続けることができるので,その間に転居先を探すことができます。
まとめ
本記事では、配偶者居住権の期間や条件について詳しく解説してきました。主なポイントを以下にまとめます:
- 配偶者居住権は原則として終身の権利だが、状況に応じて期間を設定することも可能。
- 適用条件には、被相続人の配偶者であることや相続開始時に居住していることなどがある。
- メリットとしては住み慣れた家に住み続けられることや配偶者の相続税額の計算において有利に働く場合があるが、建物の処分に制限があるなどのデメリットもある。
- 子供たちとの良好な関係を維持するためには、オープンなコミュニケーションと公平性の確保が重要。
- 権利取得の手続きには、遺産分割協議や登記申請などのステップがある。
- 登記は第三者への対抗要件として非常に重要で、怠ると権利を主張できなくなるリスクがある。
- 配偶者短期居住権は、配偶者居住権が設定されるまでの一時的な居住権を保護する。
- 配偶者居住権は令和2年4月1日以降の相続から適用される。
配偶者居住権は、残された配偶者が生涯にわたり住まいの安定を確保する重要な選択肢です。
この制度を正しく理解し、適切に活用することで、安心して豊かな老後生活を送ることができます。
読了後にすべきこと:
- 配偶者と話し合い、配偶者居住権の活用について検討する。
- 子供たちを含めた家族会議を開き、将来の住まいについて話し合う。
- 必要に応じて行政書士や弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談し、具体的な対策を立てる。
- 遺言書の作成や更新を検討し、配偶者居住権の設定について明記する。
- 遺言だけにとらわれず、家族信託という制度なども検討する。
配偶者居住権は、高齢者の方々の住まいの安定と家族の絆を両立させる素晴らしい制度です。この記事を参考に、ぜひ自分の状況に合った最適な選択をしてください。
配偶者居住権等に関する関連条文
民法ー配偶者居住権、配偶者短期居住権法令
第一節 配偶者居住権
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
(居住建物の修繕等)
第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(居住建物の費用の負担)
第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(居住建物の返還等)
第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
第二節 配偶者短期居住権
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
(居住建物の返還等)
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/
参考サイト:
国税庁 「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。