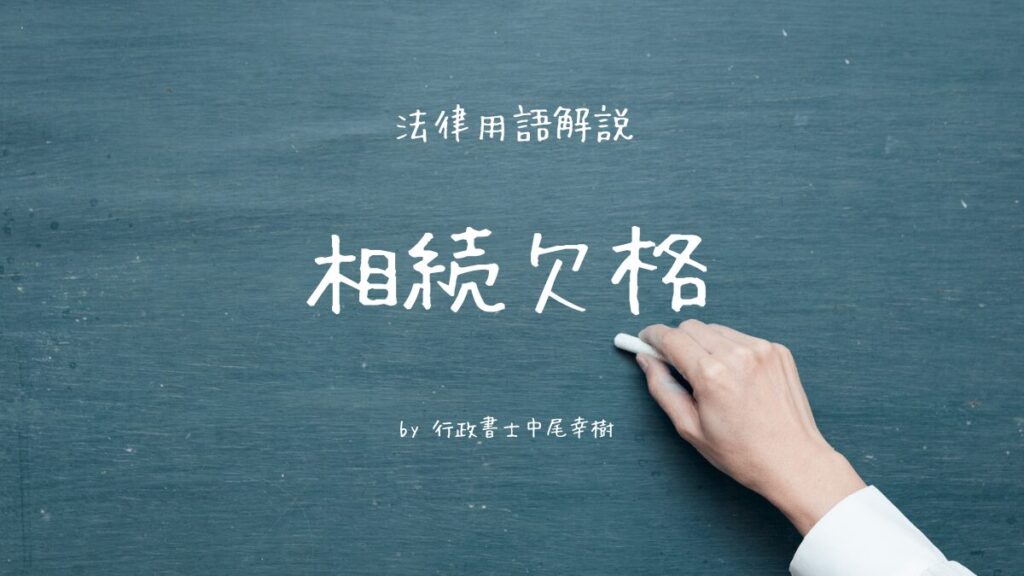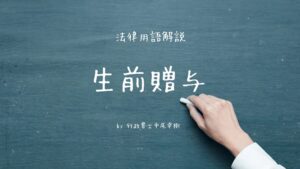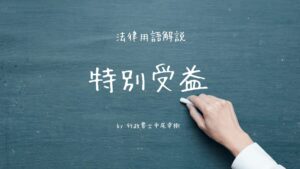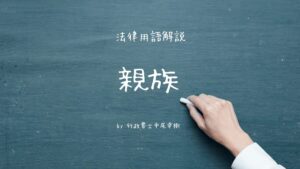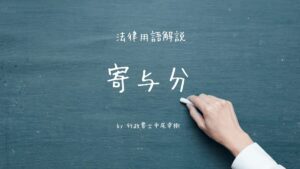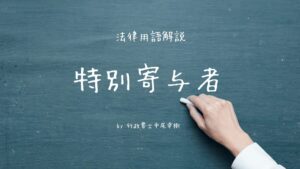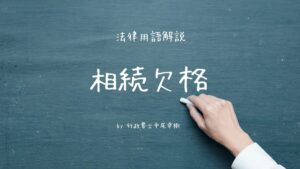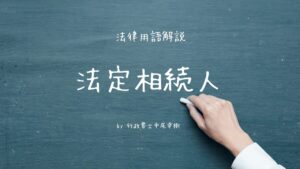相続廃除とは? 相続人の資格を失わせる重要な制度を分かりやすく解説
相続廃除とは、相続人の資格を失わせる制度です。重大な非行があった相続人に対して、被相続人が行使できる権利です。家族関係の悪化や財産の散逸を防ぐ目的で設けられていますが、その適用には慎重な判断が必要です。この記事では、相続廃除の基本的な仕組みや適用条件について、わかりやすく解説します。
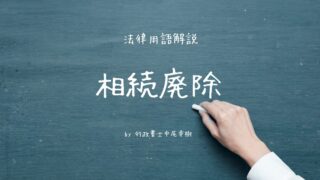
1. 相続廃除の基本的な仕組み
1-1. 相続廃除の定義と目的
相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて、特定の相続人の相続権を失わせる制度です。
この制度は、相続人が被相続人に対して重大な非行を働いた場合などに適用されます。
目的は主に以下の2点です:
- 被相続人の意思を尊重する
- 家族関係の悪化や財産の散逸を防ぐ
例えば、被相続人を虐待していた相続人がいる場合、その人に財産を相続させたくないと考えるのは自然なことです。
相続廃除は、そういった被相続人の意思を法的に実現する手段となります。
1-2. 相続廃除の法的根拠
相続廃除の法的根拠は民法第892条に定められています。この条文では、相続廃除の対象となる行為として、以下の2つが挙げられています:
- 被相続人に対する虐待や重大な侮辱
- その他の著しい非行
ただし、相続廃除の対象となるのは「遺留分を有する」推定相続人のみです。具体的には以下の人々が対象となります:
- 配偶者
- 直系尊属(両親、祖父母など)
- 直系卑属(子ども、孫など)
一方で、兄弟姉妹は遺留分を持たないため、相続廃除の対象とはなりません。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
2. 相続廃除の適用条件
2-1. 相続廃除の対象となる行為
相続廃除が認められるのは、法律で定められた特定の行為がある場合のみです。具体的には以下のような行為が該当します:
- 被相続人への虐待:身体的な暴力だけでなく、耐え難い精神的苦痛を与える行為も含まれます。
- 重大な侮辱:被相続人の名誉や感情を著しく傷つける行為を指します。
- その他の著しい非行:虐待や重大な侮辱には該当しないものの、それに匹敵する程度の悪質な行為を指します。例えば:
- 重大な犯罪行為
- 被相続人の遺棄
- 被相続人の財産の浪費や無断処分
- 極めて不道徳な行為
ただし、単に被相続人と不仲というだけでは相続廃除の理由としては不十分です。
客観的にみて、家族的信頼関係が著しく破壊されており、遺留分を失ってもやむを得ないと判断される程度の行為である必要があります。
2-2. 相続廃除の手続き
相続廃除の手続きは、被相続人のみが行うことができます。具体的には以下の2つの方法があります:
- 生前廃除:
- 被相続人が生きている間に家庭裁判所に申立てを行います。
- 必要書類(推定相続人排除の審判申立書、戸籍謄本など)を提出します。
- 裁判所で審判手続きが行われ、廃除の可否が判断されます。
- 遺言廃除:
- 被相続人が遺言書に廃除の意思を明記します。
- 被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。
なお、被相続人が高齢による認知症などで行為能力に制限がある場合でも、法定代理人を介さずに自ら手続きを行うことができます。
相続廃除が認められた場合、10日以内に戸籍の届出を行う必要があります。
- 推定相続人廃除届
- 審判書謄本及び確定証明書
- 届出人の印鑑
これにより、廃除された相続人の戸籍に、推定相続人から廃除された旨が記載されることになります。
3. 相続廃除と他の制度との違い
3-1. 相続欠格との違い
相続廃除と似た制度に「相続欠格」がありますが、両者には重要な違いがあります:
- 発生のタイミング:
- 相続廃除:被相続人の意思表示が必要
- 相続欠格:法律で定められた事由に該当すれば自動的に発生
- 対象となる行為の重大性:
- 相続廃除:比較的広範な行為が対象
- 相続欠格:被相続人殺害など、法定された極めて重大な行為に限定
- 手続きの必要性:
- 相続廃除:家庭裁判所での手続きが必要
- 相続欠格:特別な手続きは不要
- 取り消しの可能性:
- 相続廃除:被相続人の意思で取り消し可能
- 相続欠格:取り消しはできない
このように、相続欠格は法律の規定により自動的に相続権が失われる制度であり、相続廃除よりも厳格な条件が設定されています。
【相続欠格】とは?相続権を失う重大な理由と知っておくべき5つのポイント」
相続欠格とは何か、どんな場合に適用されるのか、詳しく解説しています。相続権を失う重大な理由や、相続放棄との違い、裁判例なども紹介。相続に関わる方必見の情報が満載です。専門家が分かりやすく説明しているので、安心してお読みいただけます。相続の疑問解決にぜひお役立てください。
4. 相続廃除の効果と影響
4-1. 相続人への影響
相続廃除が認められると、廃除された相続人は以下のような影響を受けます:
- 相続権の喪失:相続人としての地位を失い、遺産を相続する権利がなくなります。
- 遺留分請求権の喪失:法定相続分の一定割合が保障される遺留分も請求できなくなります。
- 戸籍への記載:相続人の戸籍に廃除された事実が記載されます。
ただし、相続廃除は取り消すことができるため、被相続人の意思次第で相続権を回復する可能性もあります。
4-2. 他の相続人への影響
相続廃除は他の相続人にも影響を与えます:
- 相続分の変更:廃除された相続人の相続分が他の相続人に分配されるため、他の相続人の相続分が増加します。
- 遺留分の計算の変更:遺留分の計算基礎となる法定相続分が変更されるため、他の相続人の遺留分も変動する可能性があります。
4-3. 相続廃除後の代襲相続
相続廃除には代襲相続が適用される点に注意が必要です。
つまり、廃除された相続人に子がいる場合、その子が代わりに相続人となります。
例えば、被相続人の子が相続廃除された場合、その子の子(被相続人から見て孫)が代襲相続人として相続権を得ることになります。
そうなっては結局は相続廃除された相続人の家族に遺産がはいることになります。
しかし、相続廃除された相続人の子に相続廃除の要件が整っていないければ廃除は出来ません。
このような場合、遺言等を活用し生前に相続対策をしておくことが必要です。
4-4. 相続権の移り変わり
相続廃除により相続権が失われた場合、その相続分は以下のように移り変わります:
- 代襲相続人がいる場合:相続権は代襲相続人に移ります。
- 代襲相続人がいない場合:他の相続人の相続分が増加します。具体的には、廃除された相続人がいなかったものとして相続分を計算し直します。
- 唯一の相続人だった場合:相続人不存在となり、特別縁故者への分与や国庫への帰属といった処理がなされます。
5. まとめ
相続廃除は、被相続人の意思を尊重し、重大な非行のあった相続人の相続権を失わせる重要な制度です。しかし、その適用には慎重な判断が必要です。
主なポイントは以下の通りです:
- 相続廃除は被相続人の意思に基づいて行われる
- 対象は遺留分を有する推定相続人のみ
- 虐待や重大な侮辱など、特定の行為が対象となる
- 生前廃除と遺言廃除の2つの方法がある
- 代襲相続が適用される点に注意が必要
- 相続欠格とは異なり、取り消しが可能
相続廃除を検討する際は、その影響の大きさを考慮し、法的な助言を得ることが賢明です。また、家族間の対話を通じて問題解決を図ることも、重要な選択肢の一つとなるでしょう。
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。