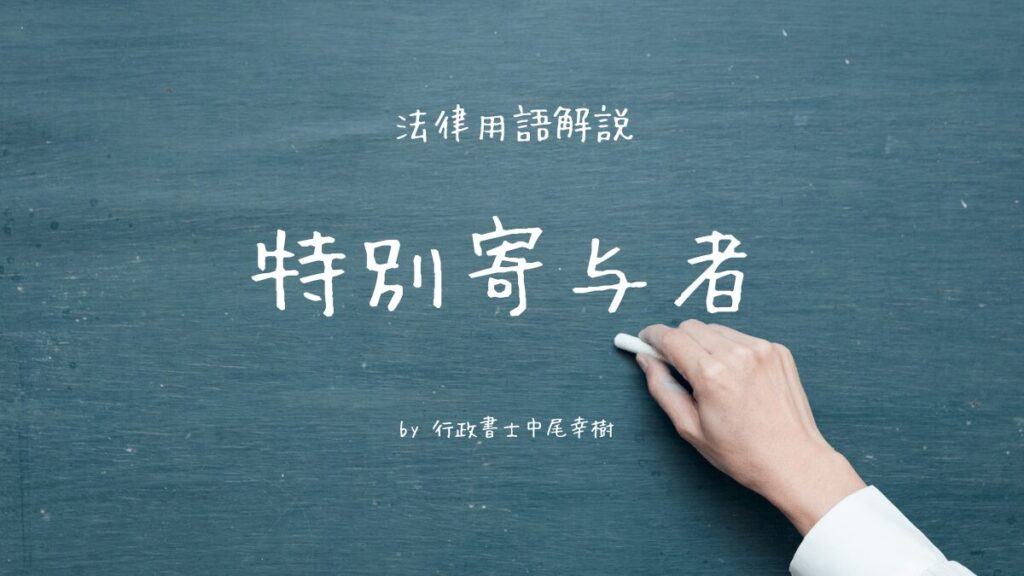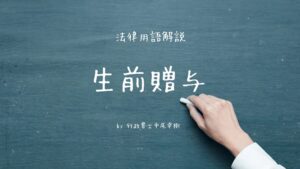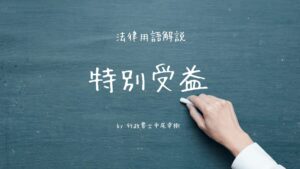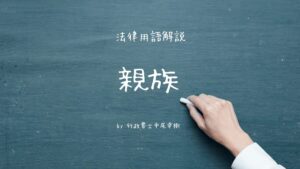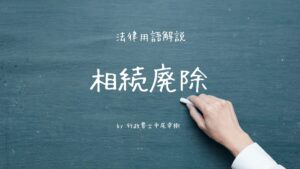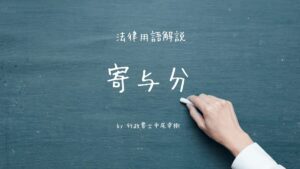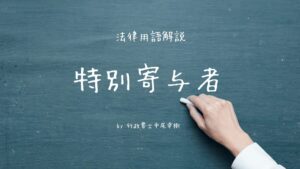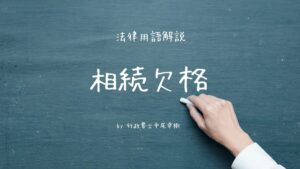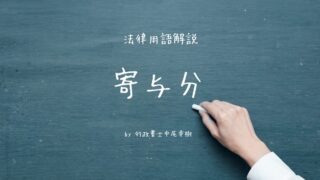
寄与分とは、夫婦の一方が相続財産の維持や増加に貢献した場合に認められる権利です。長年連れ添った夫婦の財産分与で重要な役割を果たすこの制度。遺産分割の際にも考慮される寄与分について、分かりやすく解説します。専業主婦の方や、共働き夫婦の方々にとって大切な知識となるでしょう。
- 1. 1. 寄与分とは何か
- 1.1. 1-1. 寄与分の定義
- 1.2. 1-2. 寄与分が認められる条件
- 2. 2. 寄与分の具体例
- 2.1. 2-1. 専業主婦の家事労働
- 2.2. 2-2. 事業への協力
- 3. 3. 介護と寄与分
- 3.1. 3-1. 介護が寄与分として認められる場合
- 3.2. 3-2. 介護の寄与分評価の難しさ
- 4. 4. 寄与分の算定方法
- 4.1. 4-1. 寄与分の金額はどう決まるのか
- 4.2. 4-2. 寄与分の主張と立証
- 5. 5. 寄与分と遺留分の関係
- 5.1. 5-1. 遺留分とは
- 5.2. 5-2. 寄与分が遺留分に与える影響
- 6. 6. 特別寄与制度について
- 6.1. 6-1. 特別寄与とは
- 6.2. 6-2. 特別寄与料の請求方法
- 7. 7. まとめ
1. 寄与分とは何か
1-1. 寄与分の定義
寄与分とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別に貢献した場合に、遺産分割の際に考慮される制度です。例えば、長年にわたり家業を手伝った場合や、献身的な介護をした場合などが該当します。
この制度は、相続人の中でも特に貢献した人を公平に扱うために設けられました。
通常の相続分に加えて、追加で相続できる部分が寄与分となります。
1-2. 寄与分が認められる条件
寄与分が認められるには、以下のような条件を満たす必要があります:
- 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
- その貢献が「特別の寄与」と認められること
- 無償または低額の対価で行われたこと
- 一定期間継続して行われたこと
ただし、「特別の寄与」の判断基準は厳しく、通常の親族関係で期待される程度を超える貢献が求められます。
2. 寄与分の具体例
2-1. 専業主婦の家事労働
専業主婦の家事労働は、長年にわたり家庭を支えた重要な貢献です。
しかし、寄与分として認められるには、通常の家事の範囲を超える特別な事情が必要です。
例えば:
- 夫の事業を支えるための特別な家事労働
- 家計の切り詰めによる資産形成への貢献
- 夫の長期療養中の献身的な介護
これらの場合、寄与分として認められる可能性が高まります。
2-2. 事業への協力
被相続人の事業に協力した場合も、寄与分として認められることがあります。具体的には:
- 家業を無償で手伝い、事業の発展に貢献した
- 被相続人の会社で低賃金で長年働いた
- 事業の負債を個人で保証した
ただし、正当な給与を受け取っていた場合は、寄与分として認められにくいでしょう。
3. 介護と寄与分
3-1. 介護が寄与分として認められる場合
被相続人への介護は、寄与分として認められる可能性が高い貢献の一つです。ただし、すべての介護が寄与分として認められるわけではありません。
以下のような場合に寄与分として認められやすくなります:
- 長期間にわたる献身的な介護
- 仕事を辞めて介護に専念した
- 介護のために転居や生活の大きな変更をした
- 専門的な介護スキルを活用した
ただし、同居の子どもによる通常の世話程度では、寄与分として認められにくい点に注意が必要です。
3-2. 介護の寄与分評価の難しさ
介護の寄与分を評価する際には、いくつかの難しい点があります:
- 介護の質や量を客観的に測定することが難しい
- 家族間での介護の分担状況を証明するのが難しい
- 介護期間中の被相続人の状態変化を考慮する必要がある
これらの理由から、介護の寄与分を主張する場合は、日々の介護記録をつけることや、医療機関の診断書を保管することが重要です。
4. 寄与分の算定方法
4-1. 寄与分の金額はどう決まるのか
寄与分の具体的な金額は、以下のような要素を考慮して決定されます:
- 寄与の期間と内容
- 被相続人の財産の増加額
- 他の相続人の寄与の有無
- 相続財産の総額
例えば、事業への協力の場合、以下のような計算式が用いられることがあります:
寄与分 = 年間想定給与 × (1 - 生活費控除率) × 寄与年数 × 裁量的割合
ただし、これはあくまで目安であり、実際の金額は個々の事情によって大きく異なります。
4-2. 寄与分の主張と立証
寄与分を主張する際は、以下の点に注意が必要です:
- 具体的な寄与の内容と期間を示す
- 寄与を裏付ける証拠(記録、写真、第三者の証言など)を用意する
- 他の相続人の理解を得るよう努める
寄与分の主張は感情的対立を招きやすいため、専門家のアドバイスを受けながら冷静に進めることが大切です。
5. 寄与分と遺留分の関係
5-1. 遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の相続分のことです。配偶者や子どもには、法定相続分の2分の1が遺留分として保障されています。
5-2. 寄与分が遺留分に与える影響
寄与分は遺留分の計算にも影響を与えます。具体的には:
- 寄与分は相続財産の総額から控除される
- 控除後の財産額を基に遺留分が計算される
相続の計算式(控除の効果)
【寄与分権利者の相続】多くもらえる
( 相続財産 - 寄与分 )× 法定相続割合 + 寄与分= 相続金額
【寄与分のない者の相続】少なくなる
( 相続財産 - 寄与分 )× 法定相続割合= 相続金額
つまり、寄与分が認められると、他の相続人の遺留分が減少する可能性があります。
このため、寄与分の主張は慎重に行う必要があります。
遺留分の基礎知識
相続について考え始めたものの、「遺留分」という言葉に頭を悩ませていませんか?遺言書を作成したいけれど、遺留分の計算方法がわからず、適切な相続計画が立てられないとお困りの方も多いでしょう。この記事では、遺留分制度の基本から具体的な計算方法、さらには円滑な相続のための対策まで、わかりやすく解説します。ご家族の将来のために、正しい知識を身につけ、適切な相続計画を立てましょう。
6. 特別寄与制度について
6-1. 特別寄与とは
2019年7月から施行された特別寄与料制度は、被相続人以外の親族が被相続人に対して無償で療養看護など特別な寄与をした被相続人の親族が、相続時に相続分を多くもらえるように請求できる制度です。
例えば:
- 息子の配偶者が義理の親を介護した場合
- 甥や姪が叔父叔母の事業を手伝った場合
これにより、法律上の相続人ではない親族の貢献も評価されるようになりました。
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
e-gov法令検索
6-2. 特別寄与料の請求方法
当事者間での協議でまとまればそれにより相続分を確定し、協議が調わないとき又は協議をすることができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。
特別寄与料を請求するには、以下の点に注意が必要です:
- 相続開始を知ってから6ヶ月以内に請求する
- 相続開始から1年以内に請求する
- 家庭裁判所に申立てを行う
請求できる親族の範囲は、被相続人の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までです。
【特別寄与者】制度とは?相続で貢献が認められる新しい仕組み
寄与分とは、夫婦の一方が相続財産の維持や増加に貢献した場合に認められる権利です。長年連れ添った夫婦の財産分与で重要な役割を果たすこの制度。遺産分割の際にも考慮される寄与分について、分かりやすく解説します。専業主婦の方や、 […]
7. まとめ
寄与分は、相続人の特別な貢献を評価する重要な制度です。しかし、その認定には厳しい基準があり、立証も難しいのが現状です。特別寄与料制度の導入により、相続人以外の親族の貢献も評価されるようになりましたが、請求には期限があるため注意が必要です。
相続に関する問題は複雑で感情的になりやすいため、寄与分や特別寄与料を主張する際は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
公平で円満な相続を実現するために、これらの制度を適切に活用しましょう。
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。