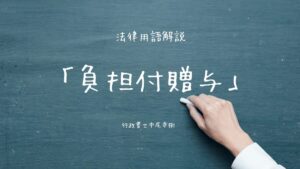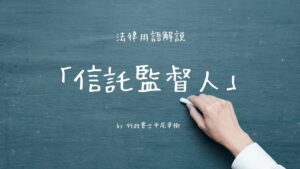制限行為能力者を知ろう:あなたや家族を守る重要な法律知識
日常生活の中で契約を結んだり、物を買ったりすることは当たり前のようにしていますが、実は法律で「できない」とされている人たちがいるのをご存知ですか?これを「制限行為能力者」と呼びます。お年寄りの方々にとって、この言葉は馴染みがないかもしれません。しかし、孫やひ孫の将来を考えると、知っておくべき大切な言葉なのです。一緒に学んでいきましょう。
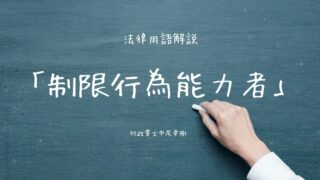
1. 制限行為能力者とは何か
1-1. 制限行為能力者の定義
制限行為能力者とは、法律によって契約などの法律行為を制限されている人のことを指します。簡単に言えば、「自分で決めて契約することが難しい人」のことです。
この制度は、民法という法律で定められています。民法は私たちの日常生活に関わる様々なルールを決めている大切な法律です。
1-2. 制限行為能力者の種類
制限行為能力者には、主に4つの種類があります。
未成年者:18歳未満の人
成年被後見人:認知症などで判断能力が全くない人
被保佐人:判断能力が著しく不十分な人(成年被後見人ほどではない)
被補助人:判断能力が不十分な人(被保佐人ほどではない)
これらの人々は、自分で判断して契約を結ぶことが難しいと法律で定められています。それぞれの状況に応じて、保護の度合いが異なります。
| 類型 | 対象者 | 本人ができること | 本人ができないこと | 成年後見人等の権限 |
|---|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が全くない人 | 日用品の購入など日常生活に関する行為 | 法律行為全般(重要な財産管理や契約など) |
- 包括的な法定代理権 - 本人の行為の取消権 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な人 |
- 日用品の購入 - 小規模な契約 |
民法13条1項に定める重要な法律行為(例: - 元本を領収し、又は利用すること - 借財又は保証をすること - 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること - 訴訟行為をすること など) |
- 重要な法律行為への同意権 - 同意を得ずにした行為の取消権 - 家庭裁判所の審判により付与される代理権(個別に指定) |
| 補助 | 判断能力が不十分な人 |
- 日用品の購入 - 通常の契約行為 | 家庭裁判所で定められた特定の法律行為 |
- 家庭裁判所で定められた特定の法律行為への同意権 - 同意を得ずにした特定の行為の取消権 - 家庭裁判所の審判により付与される代理権(個別に指定) |
後見の場合、成年後見人は包括的な代理権を持ち、本人の財産管理や契約などほぼすべての法律行為を代行できます。
保佐の場合、保佐人の同意が必要な行為は法律で定められていますが、それ以外の行為は本人が単独で行えます。また、家庭裁判所の審判により、保佐人に代理権を与えることもできます。
補助の場合、補助人の同意が必要な行為や補助人が代理できる行為は、家庭裁判所が個別に定めます。本人の自己決定権を最大限尊重する制度です。
2. なぜ制限行為能力者制度があるのか
2-1. 制度の目的
この制度の主な目的は、判断能力が十分でない人を守ることです。
例えば、物事の良し悪しを十分に判断できない人が、悪意のある人にだまされて不利な契約を結んでしまうことを防ぐためです。
2-2. 制限行為能力者を保護する理由
制限行為能力者を保護する理由には、以下のようなものがあります:
本人の利益を守る:判断能力が不十分な人が不利な契約を結ぶことを防ぎます。
社会の秩序を保つ:弱い立場の人を守ることで、公平な社会を作ります。
家族の負担を軽減する:本人が大きな損害を被ることを防ぎ、家族の心配や負担を減らします。
3. 制限行為能力者と契約
3-1. 制限行為能力者が結んだ契約の効力
制限行為能力者が結んだ契約は、取り消すことができる場合があります。これは、民法第5条から第21条に基づいています。
例えば、未成年者が親の同意なしに高額な商品を買う契約を結んだ場合、その契約を後から取り消すことができます。
3-2. 取り消しできる契約と取り消しできない契約
ただし、全ての契約が取り消せるわけではありません。
取り消しできる契約の例: 高額な商品の購入、 ローン契約、 不動産の売買
取り消しできない契約の例: 日用品の購入、小遣いの範囲内での買い物、 法定代理人(親や後見人)の同意を得た契約
4. 制限行為能力者制度の具体例
4-1. 未成年者の場合
未成年者(18歳未満の人)は、親の同意がなければ、原則として契約を結ぶことができません。これは、民法第5条に基づいています。 例えば、17歳の高校生が親の同意なしにスマートフォンの契約を結んだ場合、その契約は後から取り消すことができます。
(未成年者の法律行為)
e-GOV https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
4-2. 成年後見制度との関係
成年後見制度は、判断能力が不十分な成人を守るための制度です。この制度を利用すると、本人は「成年被後見人」や「被保佐人」となり、制限行為能力者に該当します。
成年後見人や保佐人が本人の代わりに契約を結んだり、本人の行為を助けたりします。これは、民法第7条から第21条に基づいています。
民法第7条から第21条
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(保佐開始の審判等の取消し)
第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
(被補助人及び補助人)
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(補助開始の審判等の取消し)
第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
(審判相互の関係)
第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
e-GOV https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
5. まとめ
制限行為能力者制度は、判断能力が十分でない人々を守るための大切な仕組みです。未成年者や認知症の方など、自分で適切な判断をすることが難しい人々を法律で保護しています。 この制度を知っておくことで、ご自身やご家族を守ることができます。例えば、認知症の症状が出始めた家族がいる場合、成年後見制度の利用を検討することで、その人の財産や生活を守ることができるでしょう。 法律は難しく感じるかもしれませんが、私たちの生活を守るためにあります。困ったときには、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。
法律のことばを優しく解説