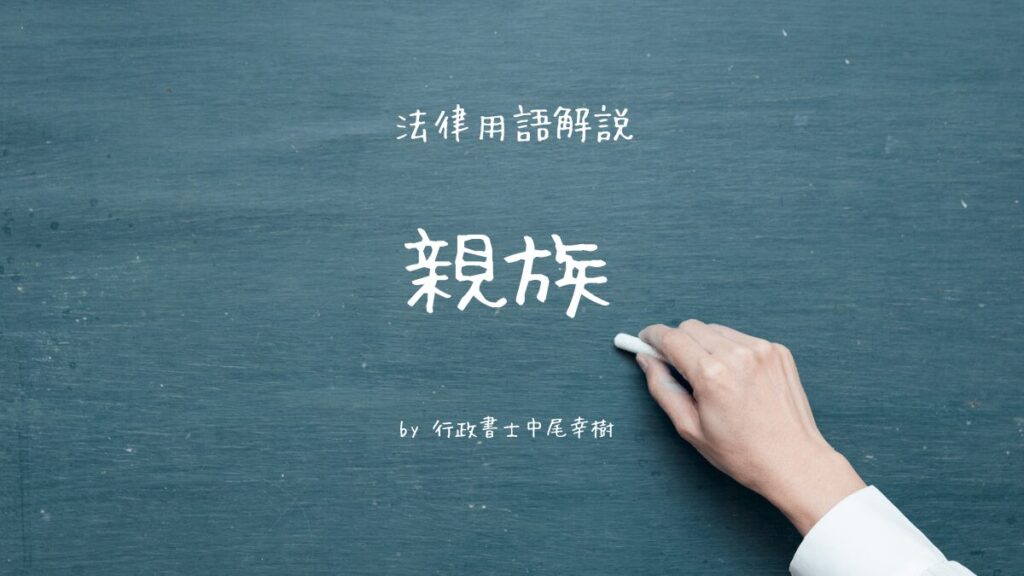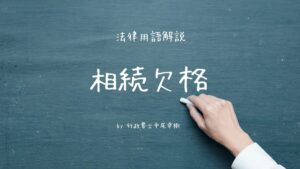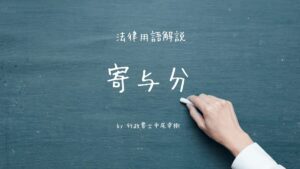寄与分とは、夫婦の一方が相続財産の維持や増加に貢献した場合に認められる権利です。長年連れ添った夫婦の財産分与で重要な役割を果たすこの制度。遺産分割の際にも考慮される寄与分について、分かりやすく解説します。専業主婦の方や、共働き夫婦の方々にとって大切な知識となるでしょう。
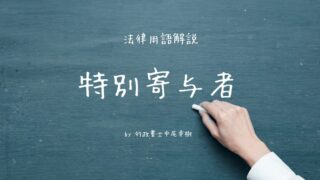
1. 特別寄与者制度とは
特別寄与者制度は、2019年7月1日から施行された新しい制度です。この制度は、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に貢献したにもかかわらず、法定相続人でない人に対して、その貢献を認めて金銭的な報酬を受け取る権利を与えるものです。
1-1. 特別寄与者の定義
特別寄与者とは、次の条件を全て満たす人のことを指します:
- 被相続人の親族である
- 相続人ではない
- 相続放棄をしていない
- 相続欠格事由に該当せず、廃除されていない
- 被相続人に対して無償で労務を提供した
- その労務提供により被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした
誰が親族にあたる?相続・手続きで知っておくべき親族の定義
親族とは何か、その定義から法律上の権利義務まで、わかりやすく解説します。血族、配偶者、姻族の違いや、相続権、扶養義務についても詳しく説明。家族や親戚との関係に悩む方、将来の相続について考えたい方必見の記事です。
1-2. 制度が作られた背景
この制度が作られた背景には、現代の家族形態の変化があります。核家族化が進み、法定相続人でない親族が被相続人の世話をするケースが増えてきました。
例えば、兄弟姉妹や子の配偶者が長年に渡って介護をしていたにもかかわらず、法律上は相続権がないという問題がありました。
特別寄与者制度は、このような方々の貢献を正当に評価し、公平な相続を実現するために導入されました。
2. 特別寄与者になれる条件
特別寄与者として認められるためには、主に2つの条件を満たす必要があります。
2-1. 無償の労務の提供
特別寄与者として認められるには、まず無償で労務を提供していることが必要です。
法律では、具体的に以下のような例が挙げられています:
療養看護 その他の労務の提供 例えば、長期間にわたる介護や、被相続人の事業の手伝いなどが該当します。
ただし、これらの労務は無償で行われていることが条件です。
2-2. 被相続人の財産の維持又は増加
次に、その労務の提供によって被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をしたことが必要です。
例えば: 介護により施設入所費用を節約できた、事業の手伝いにより収益が上がった などが考えられます。
ただし、どの程度の貢献が「特別」と認められるかは、個々のケースによって異なります。
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
3. 特別寄与料の請求方法
特別寄与者として認められた場合、その貢献に応じた金銭(特別寄与料)を請求することができます。
3-1. 請求の手続き
特別寄与料の請求は、以下の手順で行います:
支払い請求
相続開始後、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求する
協議
相続人との協議で金額を決定する
家庭裁判所申立て
協議が調わない場合や協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てる
注意点: 相続の開始と相続人を知った時から6ヶ月以内 相続開始時から1年以内 に申し立てる必要があります。
3-2. 金額の決め方
特別寄与料の金額は、以下の要素を考慮して決定されます:
寄与の時期、方法、程度 相続財産の額 その他の一切の事情
ただし、特別寄与料の上限額は、**(相続財産の総額)-(遺贈の総額)**を超えることはできません。
また、相続人が複数いる場合、各相続人は自分の法定相続分に応じた金額を負担することになります。
4. 特別寄与者制度のメリットとデメリット
4-1. 制度を利用するメリット
特別寄与者制度には、以下のようなメリットがあります:
- 法定相続人でなくても貢献が認められる
- 無償の労務提供が金銭的に評価される
- 公平な相続の実現につながる
4-2. 注意すべき点
一方で、以下の点に注意が必要です:
- 請求期限が短い(最長1年)
- 「特別の寄与」の判断基準が不明確
- 相続人との関係悪化のリスク
5. まとめ
特別寄与者制度は、法定相続人ではない親族の貢献を認める新しい制度です。
被相続人の介護や事業の手伝いなど、無償で労務を提供し、財産の維持・増加に貢献した人が対象となります。
この制度を利用するには、相続開始後すぐに行動を起こす必要があります。また、「特別の寄与」の判断には不確定要素もあるため、専門家に相談することをお勧めします。
相続は家族の問題でもあるため、金銭面だけでなく、感情面にも配慮しながら進めることが大切です。特別寄与者制度は、これまで報われなかった貢献を認める機会となる一方で、家族関係に影響を与える可能性もあります。制度の利用を検討する際は、こうした点も踏まえて慎重に判断しましょう。