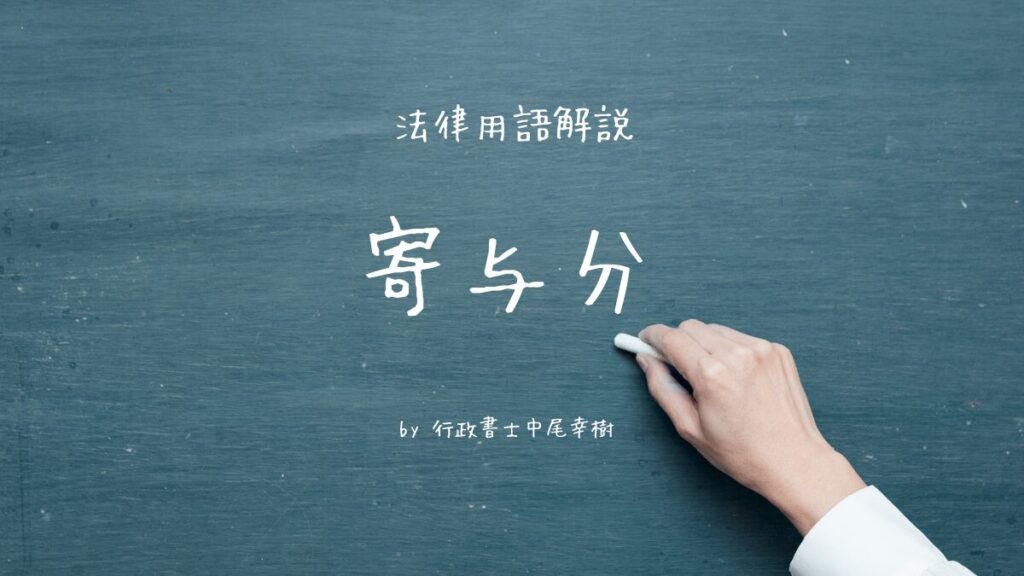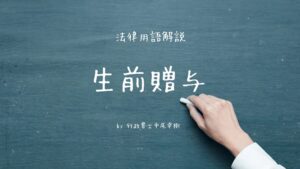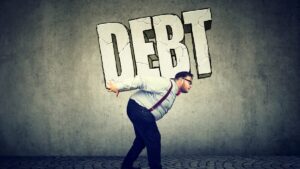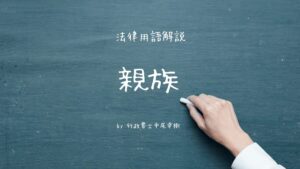「特別受益」とは?
相続の公平性を保つ重要な概念をわかりやすく解説
相続の世界には「特別受益」という言葉があります。これは、亡くなった方(被相続人)が生前に特定の相続人に対して行った贈与や、相続開始後に遺言によって与えられた財産のことを指します。相続の公平性を保つために重要な概念ですが、その仕組みは複雑で分かりにくいものです。この記事では、特別受益について分かりやすく解説し、相続に関する知識を深めていただきます。
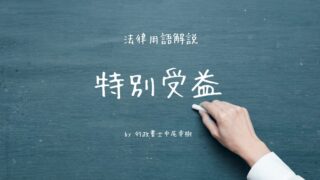
1. 特別受益の基本的な意味
1-1. 特別受益の定義
特別受益とは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、あるいは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合に、その受け取った財産のことを指します。これは民法第903条に定められています。 特別受益の対象となるものは主に以下の3つです: 遺贈(遺言による贈与) 婚姻・養子縁組のための贈与 生計の資本としての贈与
1-2. 特別受益の目的
特別受益の制度が設けられている主な目的は、相続の公平性を保つことです。例えば、ある相続人が被相続人の生前に多額の贈与を受け取っていた場合、それを考慮せずに相続財産を分配すると、他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。 特別受益の制度により、このような生前の贈与や遺贈を相続財産に加えて計算し、実際の相続分を調整することで、相続人間の公平性を確保することができます。
2. 特別受益の種類
2-1. 生前贈与
特別受益として扱われる生前贈与には、主に以下のようなものがあります:
婚姻のための贈与: 結婚する際に親から受け取る結納金や嫁入り道具など
養子縁組のための贈与: 養子縁組の際に実親から受け取る財産
生計の資本としての贈与: 独立や開業の際に受け取る資金など
ただし、これらの贈与が必ずしも全て特別受益になるわけではありません。
その贈与が「遺産の前渡し」と考えられるかどうかが重要な判断基準となります。
2-2. 遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を贈与することを指します。
相続人に対する遺贈は特別受益として扱われます。例えば、遺言で「長男に自宅を贈与する」と指定されていた場合、その自宅の価値は長男の特別受益となります。
現在の公証実務においては、遺言によ不動産を特定の人に帰属させる場合、その人が相続人でない場合は「遺贈する」と表現し、相続人である場合は「相続させる」と表現しています。遺贈と相続という遺言での言葉の違いで、不動産の移転登記を単独で出来るか、共同申請になるか、効果が変わってしまう為注意が必要です。
3. 特別受益の計算方法
3-1. 特別受益の持ち戻し
特別受益の計算では、「持ち戻し」という考え方が重要です。
これは、特別受益を受けた相続人が、その受け取った財産を一旦相続財産に戻すという概念です。
具体的には以下の手順で計算します:
価額を算出
被相続人が相続開始時に持っていた財産の価額を算出する
再計算
その価額に特別受益の価額を加える
合計額の確定
相続財産と特別受益の持ち戻しの合計額を相続財産とみなす。
相続分を計算
法定相続分に基づいて各相続人の相続分を計算する。
特別受益の価額を控除し算出
特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益の価額を控除した額を算出する
3-2. 具体的な計算例
例えば、以下のような状況を考えてみましょう:
被相続人の相続財産: 3000万円 相続人: 配偶者と子2人(長男、長女) 長男が生前に1000万円の贈与を受けている(特別受益)
この場合の計算は次のようになります:
みなし相続財産 = 3000万円 + 1000万円 = 4000万円
各相続人の法定相続分:
- 配偶者: 4000万円 × 1/2 = 2000万円
- 長男: 4000万円 × 1/4 = 1000万円
- 長女: 4000万円 × 1/4 = 1000万円
したがって、実際の相続分配は以下のようになります:
- 配偶者: 2000万円
- 長男: 0円(既に1000万円を受け取っているため)
- 長女: 1000万円
4. 特別受益と他の相続制度との違い
4-1. 遺留分との関係
遺留分とは、相続人に保障された最低限の相続分のことです。特別受益は遺留分の計算にも影響を与えます。
遺留分を算定する際には、特別受益も相続財産に含めて計算します。
ただし、遺留分の計算では、相続開始前10年以内になされた贈与のみが対象となります。これは特別受益の計算とは異なる点です。
遺留分の基礎知識
相続について考え始めたものの、「遺留分」という言葉に頭を悩ませていませんか?遺言書を作成したいけれど、遺留分の計算方法がわからず、適切な相続計画が立てられないとお困りの方も多いでしょう。この記事では、遺留分制度の基本から具体的な計算方法、さらには円滑な相続のための対策まで、わかりやすく解説します。ご家族の将来のために、正しい知識を身につけ、適切な相続計画を立てましょう。
4-2. 寄与分との違い
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に認められる追加の相続分です。
特別受益が相続分を減らす方向に働くのに対し、寄与分は相続分を増やす方向に働きます。
両者は相続の公平性を図るという点では共通していますが、その作用は正反対です。
「寄与分」って何?家事や介護をしてきた配偶者の大事な権利を徹底解説
遺産相続における「寄与分」とは何か、どのような場合に認められるのか、具体例を交えて分かりやすく解説。専業主婦の家事労働や介護の評価、寄与分の算定方法、新しい特別寄与料制度についても詳しく説明。相続で悩む方必見の情報が満載です。
5. 特別受益が問題になるケース
5-1. 相続人間での争い
特別受益は相続人間の争いの原因になることがあります。例えば、ある相続人が「兄弟が生前に多額の贈与を受けていた」と主張し、それを特別受益として計算に入れるよう求めるケースがあります。 このような場合、贈与の事実や金額を証明することが重要になります。銀行の振込記録や贈与契約書などの客観的な証拠が必要となるでしょう。
5-2. 税務上の問題
特別受益は相続税の計算にも影響を与えます。相続税の申告では、特別受益として受けた財産も含めて計算する必要があります。
ただし、相続時精算課税制度を利用した贈与については、特別受益として持ち戻す必要がありません。
この制度を利用することで、生前贈与と相続を一体的に捉えて税金を計算することができます。
6. まとめ
特別受益は、相続の公平性を保つための重要な制度です。被相続人からの生前贈与や遺贈を考慮に入れることで、相続人間の公平な財産分配を実現します。 ただし、何が特別受益に該当するか、その価額をどう評価するかなど、判断が難しい点も多くあります。相続に際して特別受益が問題になりそうな場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。 相続は家族間の問題であり、単に法律や計算だけでなく、感情的な側面も大きく影響します。特別受益の問題を通じて家族間の対立が深まってしまうことは避けたいものです。公平性を保ちつつも、家族の絆を大切にする姿勢が重要です。
\
いつでも
ご相談ください
/
わたしたちは、行政書士として【行政手続きの不安を安心に。安心をもっと身近に】を理念に活動しています。
お困りの際は一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。